
公式インタビュー ワールド・フォーカス 『ホドロフスキーのDUNE』
―フランク・パヴィッチ(監督/プロデューサー)
1975年に、アレハンドロ・ホドロフスキー監督がSF小説「デューン(DUNE)」の映画製作を開始した。が、キャストはもとよりデザインにも各界から一流のメンバーを集めながらも、1年後には制作中止に。その“事の次第”をホドロフスキー自身が語るドキュメンタリー『ホドロフスキーのDUNE』で、世界中の映画人から注目を集めたフランク・パヴィッチ監督に“伝説の監督”の素顔などを伺った。
――若いフランク・パヴィッチ監督が伝説の監督ホドロフスキーを知ったのは?
フランク・パヴィッチ監督(以下、パヴィッチ監督):サイケデリックで不思議な映画を作った監督として彼の評判は聞いていても、『エル・トポ』(69)や『ホーリー・マウンテン』(73)などの作品は長い間観られませんでした。彼がプロデューサーと喧嘩をしたために、特にアメリカではビデオにもならず、もちろん上映もなかったのです。だから、余計に観たくなり、海外で発売されたビデオのダビングのダビングを手に入れて観て、でも、映像が悪すぎて良さがぜんぜん伝わってこない(苦笑)。そんな中で唯一、日本のレーザーディスクが画像もきれいだったのですが、今度は日本語の字幕ですからスペイン語のわからない私には、何を言っているのかさっぱりわからない(笑)。とにかく、そういう風に我々若者は努力してホドロフスキーの作品にやっと出会えた。その感動や彼に対する思い入れは、You Tubeでなんでも簡単に見られる現代とはまったく違うのです。
――最初に、どのようにコンタクトをとったのですか?
パヴィッチ監督:インターネットで検索したらスペインに彼のエージェントがいることがわかったのでメールを送りました。その数週間後にホドロフスキー本人からメールが来たのですが…。僕は「断りの返事だったら、すべてが終わる!」と思うと、怖くてメールを開けませんでした。でも1週間後に意を決して開けると、「僕と話がしたいなら、パリにおいで」と書いてあってすぐに飛んで行きました。世界的に有名な、伝説的な人が目の前にいる! そのこと自体が信じられなかったし、怖かった。でもご本人は優しい方で、いろんなアイデアがあるとも言ってくれました。ただし、あることをしなければ映画化できないとも言いました。

――それはなんですか?
パヴィッチ監督:制作を担当していたミシェル・セドゥをみつけることです。ホドロフスキーとセドゥは、1976年に『DUNE』の制作中止後、1回だけパリのレストランで偶然に会っているのですが、挨拶だけをして別れています。それ以来、まったく会ってもいないし話もしていない。ホドロフスキーはセドゥが自分を嫌い、怒っていると思っていたのです。30年以上も。でも今回の映画はセドゥか持っているアートワークが不可欠であり、彼の承諾なくしては作れないと。だからこそ私にセドゥを探せと言ってきました。
――ふたりの再会の場面が本作にも映し出され、観る側としてはドキドキしました。
パヴィッチ監督:約束の時間の10分前に待ち合わせ場所の公園にやってきたホドロフスキーも落ち着かず、まるで怯えているかのようでした。私は、「ミシェルはあなたを嫌っていない」と伝えていたのですが。それが証拠に、私が初めて訪れたセドゥのオフィスには『DUNE』の制作時に描かれた絵がメインルームや会議室に飾ってありました。さらにはホドロフスキー自身がサインをした『ホーリー・マウンテン』のポスターまで飾ってあったのです。セドゥは毎日オフィスに通い、『DUNE』とホドロフスキーとの思い出の中で暮らしてきたのだと、私は胸が熱くなりました。ともあれ、待ち合わせの時間ぴったりにセドゥが公園に現れました。ふたりは黙って抱き合いました。それは本当に美しい時間であり、美しい映像でした。
――再会がきっかけで、おふたりは再びコラボをしました。監督の貢献は大きいですね。
パヴィッチ監督:この映画が完成した数週間後、みんなが夕食に集まった時にホドロフスキーが「また映画を作りたい」と言うと、即座にセドゥがプロデューサーを名乗り出たのです。そこから話はトントン拍子に進み、今年のカンヌ映画祭でも上映された『リアリティのダンス』が誕生したのです。僕のおかげでできたとは言いたくありませんが、35年間会わなかった、憎み合い愛し合っていたふたりを再会させた役割は大きかったと自負しています。
――さて本作の製作開始となると、自説を曲げない頑固なアーティストであるホドロフスキーから撮影中に「ここはこうして欲しい」というような意見はありましたか?
パヴィッチ監督:正直、最初は私も「どれくらい口を出すのかな?」と思ったりもしました。でも彼はいっさい口を出さなかった。私の思い通りにさせてくれました。ですから、逆にこれは私の監督作だけれど、ホドロフスキーの子供でもあると思っていました。
――完成品を観たときのホドロフスキーの反応が気になりませんでしたか?
パヴィッチ監督:カンヌ映画祭のプレミア上映で彼と奥様と一緒に観ました。僕は、上映中も彼の反応が気になって気になって(笑)。でも、ラストの方で彼が涙を流しているのに気がついて感動しました。上映後に感想を伺ったら、「It’s perfect!」と。それだけで十分です。とても嬉しかったですね。それにホドロフスキーが札束を握って、「これはただの紙切れである」というシーンは何回観ても感動してしまうのですが、あの姿に強くインスパイアされて、今後は私も素晴らしい映画を作らなければとあらためて思いました。
――偶然にミック・ジャガーやサルバドール・ダリとパーティで出会って出演交渉をしたり、食いしん坊なオーソン・ウェルズを高級フランス料理で釣って出演のOKをとったり。奇想天外なエピソードが綴られていますが、入りきらなかったおもしろエピソードはありますか?
パヴィッチ監督:一番気に入っているものをひとつ紹介します。『DUNE』は皇帝の裏切りによって自害した公爵の息子ポールが主人公ですが、その母親役にシャーロット・ランプリングを起用しようと思い脚本を送ったそうです。しかし、そこには公爵を挑発するために悪の軍団が全員ズボンを脱いで放尿するというシーンが書かれていて、彼女もその場にいる設定でした。それを読んだシャーロットは、「こんな映画には出られないわ」と断ってきたそうです。そのエピソードを僕に話し終わったホドロフスキーは、「ランプリングは芸術をわかっていない」と、ひと言(笑)。

――最後に、ホドロフスキー監督の作品も含め、一番好きなところは?
パヴィッチ監督:彼は決して妥協しない。自分のビジョンを持ち続けています。そして、もしそれが実現できなければ、ほかの手段をみつける。映画監督だけではなく、コミックの原作を書いたり小説を書いたり。時にはタロットカードやマジックをして創作意欲を具現化していきます。そこがデヴィッド・リンチと違うところです。ホドロフスキーが挫折した後に、『デューン/砂の惑星』を監督したリンチの才能は否定しませんが、彼はコマーシャル撮影もしている。ホドロフスキーはそういう風に自分の才能を売りに出したことはないのです。事実、昨年(ニコラス・ウィンディング)レフン監督がヴェルサーチのコマーシャルを撮ったのを知って、「今度コマーシャルの撮影をしたら友人関係を断ち切る」と言いました。彼は決して魂を売ることはしないのです!
取材/構成:金子裕子(日本映画ペンクラブ)
ワールド・フォーカス
『ホドロフスキーのDUNE』
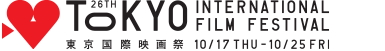







 Check
Check
