
公式インタビュー コンペティション 『ハッピー・イヤーズ』
―ダニエレ・ルケッティ監督
パパとママはいつからギクシャクしていたのだろう。ハンサムな芸術家のパパの自分勝手に、ママもついには実力行使に出る。1970年代のイタリアを背景に、男の子の視点を大切にした『ハッピー・イヤーズ』。「自分の作品を持って日本に来るのは4回目」という、来日したダニエレ・ルケッティ監督にお話を伺いました。
――父親役のキム・ロッシ・スチュワートはアントニオーニ監督の『愛のめぐりあい』で日本にもファンが多いと思います。彼の起用は、あなたのお父様に似ていたから?
ダニエレ・ルケッティ監督(以下、ルケッティ監督):身体的には結構、似ていると思います。ただ、それに気づいたのは、メイクとか衣装を選び終えた後でした。キムは最初、ニュートラルな感じで現れ、自分の個性を出そうとはしていなかった。似ているとは思ったけど、よく考えてみるとそんなに似ていなかったかもしれないな(笑)。
――この物語はどのように形になっていったのですか?
ルケッティ監督:18年前に50ページぐらいの家族に関するメモを取り始めて、映画を撮る度に読み返していたんです。で、昨年、本作を撮ろうと思った時に読み返してみたら、例えば祖父・祖母・大叔父・大叔母といった人々のことは書かれていたのに、一番自分に身近な両親とか兄弟に関しては全く抜けていたんですね。その部分が大きな穴になっていた。でも、そのことで自分にとっていかに家族というものが重要なのかと気づいたんです。
この映画を撮るときには現実の両親の姿を描こうと思ったわけでなく、それよりは歴史、あの時代の家族というものを描こうと思った。その意味でより自由に描くことができたし、逆に両親のキャラクターを活かすこともできました。それが、本作を撮る時の鍵になったと思います。
――物語は1974年のイタリアを舞台にしていますが、ヨーロッパでは、例えば53年のスターリンの死、68年のフランス五月革命のように、エポックになる年が時々登場しますね。
ルケッティ監督:74年というのはイタリアにとって非常に重要な年なんですよ。というのは、離婚の法案が決まった年ですから。もちろんカトリック教会はそれに反対していて、法案が通らないようにしていたけど、国民投票が行われて結局、法案が通った。カトリックが負けたことで、イタリアは思ったよりもカトリックの国じゃないということがわかった年だった。自分でもよく覚えているのは、もしそれが通ってしまったら、うちの親は離婚してしまうんじゃないかと。イタリアの大体の子供たちは、うちの親が離婚したらどうしようと悩んだ年でもありました(笑)。
ただ、イタリア人は実際に重要なことに関しては、宗教的な判断はしない。たとえ信仰に篤い人たちでも、市民としてチョイスしなければならない時は頭で考えて選ぶ。イタリアというのは非常に矛盾に満ちた国なんです。ベルルスコーニ前首相にしても、「自分はカトリックだ」と言ってますからね(笑)。性的にはとんでもないことをしていても、カトリックというだけで守られる。モラルはその時々で変わっていくんでしょうね。
――本作は一度「FINE(終わり)」が出て、その後、いろいろな種類の映像が出ますが、あれはどういう思いを込めたのですか。
ルケッティ監督:あれは直感的にやりました。映画が終わって、そこまでに観客が感じたエモーション、感情を少し抑える、鎮める瞬間が必要だなと思っていて、そういう時にああいうイメージを重ねたりすることが有効かなと考えました。あれは若干、当時の前衛的な映画とか手法にもちょっと似ていたかもしれないし。重要なものは含まれていないんだけれども、それを重ねていくことで映画の内容や起こったことを振り返る。説明じゃなくて、イメージとしてバーッと思い出していくようなものにしたかったんです。
――当時の前衛的な映画とは?
ルケッティ監督:イタリアではスキファーノという監督が前衛作家としてとても有名で、当時そういう実験的な作品をシネクラブやギャラリーなどに観に行っていたんです。もちろんアメリカ映画などもたくさんあって。15~16歳の頃、ほとんど名前も意識せずにそういう作品をたくさん観てすごくびっくりしましたよ。

――それ以前の映画体験とはどのようなものだったのでしょう。
ルケッティ監督:当時のイタリア人というのは、ほとんど毎日映画を観に行っていました。半分は商業映画でしたけどね。僕も14歳の時には、毎日、朝から映画館に行って最初の1回目はおばさんたちと観て、2回目はおじいさんたちと、3回目はお母さんたちと、といった具合に1日に3~4回、繰り返し同じ映画を観ていたんです。特に母方のおばさんが、アントニオーニだとかベルイマンのようにクセのある映画が好きで、よく連れて行ってくれたんです。両親はそんなこと露知らず、でしたが(笑)。74年にはベルイマン監督の『ある結婚の風景』を観せられてすごくびっくりした。最初から最後まで会話だけで成り立つ、そんな映画があるんだということにね。当のおばさんは「理解不能な映画ね」と言っていたけれど、僕自身は、何かわかるような気がしていました。ただ、それがなんだかはわからないんですけれども。
――監督は東京国際映画祭ではもうお馴染みの方ですが、遠路はるばる来てくださる理由は?
ルケッティ監督:自分の映画を持ってくるのはこれで4回目になると思うんですけれども、毎回考えるのはイタリアと日本の距離はこれだけ遠いのに、物語の中に入るということに関してはそれとは関係ない。人間の物語であって、そこに人物がある限り違いということは全く感じられなくて距離はゼロになる。それに対して非常に驚きますね。イタリア映画界にも、パオロ・ソレンティーノのように国際的に評価される監督もどんどん出てきていますし、反対にいろんな国の映画がイタリアにいても観られる。人間の物語である限り、すぐにその中に入っていく事ができるんですよ。
――イタリア語と日本語は母音の共通点があって、日本人にも親しみを覚えやすい言語ですが監督ご自身が好きなイタリア語は何ですか?
ルケッティ監督:アハハ(笑)。自分の台詞じゃなくて、ウディ・アレンの『ハンナとその姉妹』から引用しましょう。自分の母国語のことはすぐには出てこないから。ウディ・アレンいわく、「è benigno(エ・ベニーニョ)」という「良性」という言葉を挙げていました。例えば腫瘍があってそれが良性だとわかる、といった時に使う言葉です。で、その次に好きな言葉が「ti amo(ティ・アーモ)」、つまり「愛している」だとか(笑)。
――監督のそうしたユーモアのセンス、映画の中の父親の展覧会のシーンでも顕著でしたね。母親との語られていない感情の交流ですが、でも何かがおかしくて。
ルケッティ監督:あのシーンは、脚本では最初いろんな形で用意していて、唯一決まっていたのは母セレーナが(モデルたちに対抗して)裸になるということだった。父グイドがそれに対してすごく動揺するというのがポイントだったんです。それ以上は撮影の場できっちり決めました。どういうふうにやっていくか、ふたりの間ですごく強烈な感情が湧き上がるわけですが、そこまで演出していって何が出てくるかというのを掘り下げていくプロセスが自分にとってとても大きかった。
あのシーンのインスタレーションに関しては、たとえ笑えたとしても決して現代アートを馬鹿にしているわけではなくて、真面目に撮ったつもりです。イタリア映画では、しばしば現代アートをおちょくるような撮り方をすることがあるけれど、僕自身はやはり現代アートも素晴らしいものだと思っていますから。もっとも、やはり滑稽な部分もあの場面にはあって、そこのバランスをとるのが少し難しかったですね。
取材/構成:佐藤友紀(日本映画ペンクラブ)
コンペティション
『ハッピー・イヤーズ』
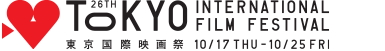







 Check
Check
