
ワールド・フォーカス『愛を語るときに、語らないこと』:10/20(日) Q&A
盲目の少女フィトリは20歳。聴覚障害のエドに想いを寄せている。弱視のディアナは失明したアンディカが好きだが、アンディカは元カノのガディスのことが忘れられない…。障害者の学校を舞台に、年頃の若者たちの愛を優しく見つめた青春群像劇。
気鋭の女性監督モーリー・スルヤ監督の第2作で、時ににこやかに、時に真剣にまっすぐな思いを伝える姿が印象的だった。プロデューサーのラマ・アディさんが「ずっと東京国際映画祭で上映できる作品を作りたかった」と語ると、場内は静かな拍手に包まれた。
登壇者:
モーリー・スルヤ監督(監督/脚本)、ラマ・アディさん(プロデューサー)、ファウザン・ジドニさん(プロデューサー)、ケルヴィン・ヌグロホさん(編集)、ゼケ・ハセリさん(音楽)
――皆さん、ようこそ東京へお越し下さいました。初めにご挨拶をいただけますか?
モーリー・スルヤ監督(以下、スルヤ監督):上映時間といい、タイトルといい、長い映画を観て下さり、ありがとうございます(笑)。東京国際映画祭に来て、このセッションに参加できることを、とてもうれしく思います。

ラマ・アディさん(以下、アディさん):この映画は『フィクション』(08)に続いて、モーリーと私たちが組んだ作品です。私たちは長いこと、東京で上映できる映画を撮りたいと思っていました。実現できたことを、とてもうれしく思います。

ファウザン・ジドニさん(以下、ジドニさん):ありがとうございます。

ゼケ・ハセリさん:天気がよくありませんが、映画祭を楽しんでいます。皆さんも映画を楽しんでくれたらうれしいです。

ケルヴィン・ヌグロホさん:この映画を観て下さり、ありがとうございます。難解に感じられるかもしれませんが、映画を理解していただき、さらに、よい評価をいただければ幸いです。

――盲学校を舞台にして、映画を作ろうと思った狙いを教えてください。
スルヤ監督:盲学校を舞台にした若者たちの青春群像というアイディアは、以前から温めていたもので、2010年に企画をスタートさせました。
この映画は、私自身の幼い頃の記憶がヒントになっています。いっしょに育った親戚の男の子がいたのですが、彼は目が見えませんでした。寄宿制の盲学校で学び、週末には家に帰ってくるという生活をしていました。その学校は、私には変わった世界に見えました。子どもたちはみんな、歌を歌うことと、音楽が大好きでした。
――エドを演じた俳優のニコラス・サプトラさんは健常者ですが、ほかの出演者の方は、実際にハンディを負った方々をキャスティングされているのでしょうか?
スルヤ監督:弱視のディアナ、全盲のフィトリ、黒メガネをかけていたアンディカ、そして女優のオーディションを受けていたマヤ、この4人については健常者の女優が演じています。ほかにも健常者の方が出ていますが、そのなかには新人もいるし、ニコラス・サプトラのようなベテラン俳優もいます。盲学校で勉強している生徒さんは、視覚障害のある方々です。映画のなかで、エドがシェイクスピア劇のビデオを見る場面がありましたが、それに出てくる女優さんも口のきけない方です。
――とても心温まる映画でした。目の見えない子がバレエを踊るエピソードがありましたが、どうしてあのシーンを入れたのでしょうか?
スルヤ監督:この映画を好きになってくださり、ありがとうございます。私とプロデューサーのラマとで、ストーリー・メイキングにかなり長い時間をかけたのですが、その時に、映画の限界に挑戦したいという話をしました。
例えば、目の見えない人物が愛を語るとき、どんなことを語るのか。また、ディアナの目が見えていて、見えているディアナがバレエを踊ったとしたら、今と同じ幸せを感じることができただろうか。
フィトリとエドの恋愛も同様です。もしフィトリの目が見え、エドの耳が聞こえていたとしたら――2人とも健常者だったら――、彼らの大事な瞬間は、健常者同士でも味わえただろうか。そういうことを描いてみたかったのです。現実と仮想の2つの事柄を考えて描こうとしました。
アディさん:現実ではない、もうひとつのリアリティを表す場面を付け加えるとしたら、どのような場面がいいだろうかと2人で考えていたのです。モーリーがちょうど東京にいたときでしたが、ある場面を思いついて、どうだろうと電話をかけてきたことがありました。私はもちろん、「モーリーの自由にやっていいよ」と答えました。
――もうひとりのプロデューサーである、ファウザンさんは映画を作っていく上で、どういう関わり方をされていたのでしょうか?
ジドニさん:私は主に、マーケティングとプロモーションを担当しています。
アディさん:この映画はサンダンス映画祭でワールド・プレミアを開きましたが、ファウザンがセールス・エージェントと話をまとめ、僕がモーリー監督と上映に立ち会うという役割分担でした。
――オーディションと途中の場面、そして最後に、「きらきら星(きらきら星変奏曲)」が登場します。インドネシアの国歌を斉唱する場面も印象的でした。これらの曲を使った理由についてお聞かせください。
スルヤ監督:映画のなかで使った曲はどれも、インドネシアではとてもポピュラーな曲です。たとえば冒頭の場面に使った「かもめの歌」は1970年代末に大流行した流行歌ですし、小さな女の子が手話で歌う「学校に出かけます」という曲も、「父母や友だちを大切にします」という、とても大事なことを歌った歌です。そういう、インドネシアの人が誰でも知っている歌を盛り込むようにしました。「きらきら星」ついては、純粋さを表したかったという気持ちもあります。
国旗掲揚の場面がありますが、これは私が幼い頃、友だちを盲学校に連れて行っていた時から現在に至るまで、毎週月曜の朝7時に行われている儀式です。国を敬う気持ちを表しているわけですが、映画の舞台になっている盲学校という小さなコミュニティでも、こうした儀式が行われていることを表したかったのです。
ワールド・フォーカス部門
『愛を語るときに、語らないこと』
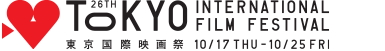







 Check
Check
