-
『がんばればいいこともある』(08/TIFF08最優秀女優賞受賞作)以来5年振りのTIFF出品となる名匠フランソワ・デュペイロン監督のインタビュー。
2012年にセザール賞の「最も期待される若手俳優賞」を受賞した主演のグレゴリー・ガドゥボワや彼が演じる特異なキャラクターについて語っていただきました。

『魂を治す男』
――作品の温かさに、とても感動しました。アイデアはどのように生まれたのでしょう。
フランソワ・デュペイロン監督(以下、デュペイロン監督):なぜかわからないんですが、ある日、アイデアが湧いてきたんですね。
監督というのは、自分のあまり合理的でないところに目を向けさせる仕事だと思います。例えば、俳優が演技をしているのを1ショット、2ショット、3ショットと撮っていくわけですけれども、その中のあるショットをより良いと感じる理由が、なぜかわからないという事と同じように。
――主人公のフレディは人を治す力を持っていながら、自分自身の人生に行き詰まっています。主人公をヒーラーにすることによって、人間は魂を救ってくれる人が必要だということがより明確になりますよね。
デュペイロン監督:その通りだと思います。人間には、自分を傷つけてしまう人と、自分の心地よさを作り上げていく人の、両方がいます。映画も同じです。自分に心地いいものを作っていって、最終的に観る人もそう感じてくださればいいなというのが、私の映画の作り方。
先ほど「感動した」と言われましたが、フランス語では「感動した」という時に、「私の胸・心を打った」という言い方もあります。「触る」というような行為が言葉の中にあるわけなんです。日本語では「治す」ことを、「手を置く」という意味の「お手当て」と言う表現があるように、私は映画を通して何かを治そうとしているのかもしれません。
――自分に心地よいものを作っていく中でも、製作中に大変なことはありましたか?
デュペイロン監督:一番大変だったのはお金が集まらなかったことです。「これではもう映画ができないから引退してもいい」と友人に言ったら、その人が去年の12月にプロデューサーに電話してくれたんです。おかげで、少ないながらも予算を出してもらえたし、プロデューサーがついたことですべての問題は解決しました。お金は少なかったけれど十分という感じでしたし、天気も俳優のことも全然困難なことはなかった。
こういうことは、ここ20年とか25年とかのキャリアの中で2回目ですね。決定するまでは悪夢のようでしたが、「やる」と決定したらすごくスルッと簡単にいきました。

――キャスティングも素晴らしいですよね。葛藤を抱えながらも、人としての温かさが伝わるフレディ役は、最初からグレゴリー・ガドゥボワと決めていたんですか。
デュペイロン監督:どの監督も予算がつくように、最初は有名な俳優にオファーするものなんですよ(笑)。私も、愚かにも最初は有名な役者にオファーしたんですね。でも、みんなに断られて、もう映画はできないだろうと思っていたんですが、ある晩、グレゴリーのことが頭に浮かんだんです。彼の舞台を見ていいなと思っていましたから。そこからは夢のようで、「ああ、彼は“真実”を私にもたらしてくれるな」と感じるようになった。
素晴らしい俳優ですし、この作品の若いふたりの女優と同じように、今後のフランス映画で活躍していくでしょう。シナリオというのは磁石みたいなものなんですね。それを読んで、何か自分と繋がるものを感じた人をどんどん吸い寄せていくんです。あんまり考えすぎないで、事に任せたほうがいいですね。
――グレゴリー・ガドゥボワはとても恰幅がいいですが、彼がフレディ役になったことで脚本に変更はありましたか。
デュペイロン監督:全くないです。それがまた映画のいいところで、この映画は私が書いた小説が原作ですが、彼が彼として演じることで、小説になかった何かをもたらしてくれました。
――パンクが流れるオープニングといい、全編にわたって音楽がとても印象的です。
デュペイロン監督:オープニングの曲はニーナ・ハーゲンですが、とても意外性がある音楽だと思います。この作品の音楽は、何かを描写している音楽ではなく、私たちを引き込み、聴こえなくなると「あれっ?」と思わせ、耳をそばだてさせるもの。俳優というよりはフレディという役がずっと観客に近づいてくる音楽だと思います。
小説にもいろいろなスタイルがありますが、私が撮ってきた映画はみな、一人称の「私は」で語られる私小説なんです。まさにこの音楽も俳優のような感じで、「私」を表しているんじゃないでしょうか。
――原作小説も同じタイトルですか?
デュペイロン監督:小説のタイトルは「Chacun pour soi, Dieu s’en fout(それぞれの人はそれぞれに任されている、神様は関心がない)」です。「それぞれの人がそれぞれ」とは、エゴイストになれという意味ではなく、自分にピッタリくる人は誰かを探しましょうということ。
自分の家ではうまく育たない植物が隣の家ではよく育つこともあるように、人間にも相性がある。環境や付き合う人を変えてみたら、なんとなくうまくいったり、自分らしくいられたりするというお話なんです。

取材/構成:杉谷伸子(日本映画ペンクラブ)
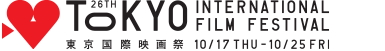







 Check
Check
