街道沿いのモーテルの管理を任された少年。そのモーテルで男を待つ女性。年の離れたふたりの男女の心のすき間を、ゆったりとしたテンポと温かいタッチで描くヒューマンドラマ『エンプティ・アワーズ』。
アジアン・プレミアの為に来日したアーロン・フェルナンデス監督と主演のクリスティアン・フェルレルさんに話を聞きました。

――とても穏やかでありながら多感な少年の心模様を丁寧に描いた青春映画ですが、監督は、何をきっかけに本作の脚本を書き始めたのですか?
アーロン・フェルナンデス監督(以下、フェルナンデス監督):場所からですね。小さなモーテルが点在するベラクルスの海岸通を車で走っていた時に、ここで青春映画を撮ったらどうだろうと思ったのです。そこで、じっくりロケハンをして舞台となったモーテル“PALMA REAL”をみつけて、同時にそこで暮らす人々も観察して、物語を書き始めました。
――『エンプティ・アワーズ』というタイトルの意味は?
フェルナンデス監督:日本語にこれと同じ言葉があるのかはわかりませんが、英語タイトルを訳せば「空虚な時間」となりますよね。でも、私が表現したかったのは、一時的に止まった時間です。叔父の入院で小さなモーテルの留守番をすることになったセバスティアン(17歳)が、あまりやることもなくて、休むというか、一瞬立ち止まるというか。それによって逆に、濃密な時間を心に刻んでいくという感じです。僕としては表面的にはたいしたことも起こらない退屈な時間の流れの中に、実はとても小さなことが起こっている。それが見えない人もいるけれど、見える人には見える。そして、その小さな出来事が積み重なっていって、エンプティな時間が埋まっていくというか、大きく動き始めるというか…。そのあたりが、僕のトリックとでもいいましょうか。
――クリスティアン・フェルレルさんがセバスティアン役に決まったプロセスは?
クリスティアン・フェルレル(以下、フェルレル):最初は僕と同じような年頃の俳優たちが集められたオーディションがありました。その中で僕は、自分の人となりを一生懸命にアピールしました。それから監督とは2、3カ月ごとに会って話をしたんです。結局、1年かかってやっと決まったのです。
フェルナンデス監督:僕には、具体的なセバスティアン像がありました。それは、海岸地方の地元の人々に近い顔をした若者で、自然にあの場所になじめること。もちろん、繊細さも不可欠です。でも、キャスティングが長引いたのは、俳優が見つからないからではなかったのです。とにかく資金集めに苦労して、撮影開始までに1年以上かかってしまった。なにしろ途中で全額を集めるのが無理だと思い、結局、見切り発車で撮影を開始しましたから。やはり、映画を作るのは大変ですねぇ(苦笑)。

――寡黙なセバスティアンの揺れ動く心を表現するのは、難しかったですか?
フェルレル:僕はメキシコで数本の映画に出演したけれど、暴力的であったり、テンションをあげっぱなしの役だったり。だからこの役は、これまでと正反対の人物像だと思ってとても興味を持ちました。でも、戸惑いはなかったです。最初からはっきりしたビジョンが監督にはありましたから。大げさではなく、物語もゆっくりと進む。それでいて非常に微妙で緻密な描写です。演技に関しては、モーテルの客の女性ミランダと少しずつ惹かれあっていく、その微妙な心の動きを大切にしました。
フェルナンデス監督:演技について言えば、彼の言う通りです。オーバーなアクションをしないように、できればなにもしていないように見えて、もっと内面が湧き出るような演技を求めました。クリスティアンもミランダを演じたアドゥリアナ・パスもがんばってくれました。
――魅力的なアドゥリアナとのベッド・シーンがありましたが?
フェルレル:実は、撮影中はモニターもラッシュも俳優には見せないというのが監督のポリシーだったので、演じていてもどう見えるかは最後までわからなくて(笑)。だから初めて完成品を見た時には、撮影のときのあれこれを思い出して感激しっぱなしでした。しかも、見るたびに違ったところに目が行ってしまうので冷静になれないです。すべてが難しかったけれど、やはりベッドシーンが一番難しかった。スクリーンで見るのも恥ずかしかったし…。

――深夜勤務の老人の犬が“マヌケ”という名前だったり、ヤシの実売りの少年との駆け引きだったり。小さな笑いがちりばめてあるのも秀逸でした。
フェルナンデス監督:私が、いつも映画をどういうコンセプトで作っていくのかというのを説明する時に例に出すのが、印象派の絵画なのです。いろんな色を重ねて絵画を描くように、ひとつひとつ小さなもの、状況とか、小さな感情とかが積み重なって大きな絵になる。そこを意識しているのでユーモアも不可欠なのです。
――先ほど、資金集めに苦労されたと伺いましたが、いちばん困難だったのは?
フェルナンデス監督:いま振り返ってみれば、本当の危機的状況というのはなかったと思います。それは、映画作りはマラソンのようなもの、100メートル走るようにはいかないと覚悟していましたから。どれだけ忍耐強く事が進められるか、長い期間エネルギーを維持して、信念を貫けるかそれが勝負だと…。資金繰りについては、ひとつひとつドアを叩いて企画を説明していかなければいけないので大変ではありました。こんな低予算の映画ですら、全額が集まらないままに撮影に入らなければなりませんでしたから。それでも、こうやって完成できた事は嬉しい限りです。しかも、文化や映画に大きな興味と敬意を抱いて憧れ続けてきた日本に来られて、東京国際映画祭に参加できた。もう、僕にとっては、ここにいること自体がグランプリを受賞したぐらいの価値があると思っています。
取材/構成:金子裕子(日本映画ペンクラブ)

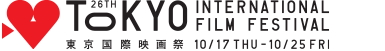







 Check
Check
