
『捨てがたき人々』
榊英雄監督は現役の俳優でもある。PFFスカラシップ作『この窓は君のもの』(1993)でデビューし、北村龍平監督の『VERSUS-ヴァーサス』(2001)で存在感を発揮。その後、主役から脇役までこなせる実力派として活躍してきた。今年、俳優生活20周年を迎え、河瀬直美監督の最新作への出演も決まっている。
監督業は自主映画畑から出発し、『GROW-愚郎』(2007)で商業作デビュー。『ぼくのおばあちゃん』(2008)が第21回東京国際映画祭〈日本映画・ある視点〉に選出、『誘拐ラプソディー』(2009)で第20回日本映画批評家大賞・新人監督賞に輝いた。『トマトのしずく』『木屋町DARUMA』が今後公開を控えており、いま最も伸び盛りの監督と言えるだろう。
この度、コンペティションに選出された『捨てがたき人々』は、『浮浪雲』『アシュラ』『銭ゲバ』で知られる、ジョージ秋山の同名漫画を映画化した作品だ。生きるのに倦み果て、所詮、人間は自己の快楽欲求を満たすだけの生き物に過ぎないとする狸穴(まみあな)勇介と、笑顔で人に接すれば苦境を抜けだせると説く新興宗教の信者、岡部京子が肉体関係を結び、やがて愛を育み、煩悩と理想の愛の狭間であがく姿を振り切ったレンジで描いている。43歳にして新境地に挑んだ監督に話を伺った。
————タイトルが示すとおり、これは煩悩を捨てられない人々の物語です。人間の煩悩は数えたら切りがありませんが、とりわけセックスに焦点をあて、真の愛情を望みながらセックスに溺れる哀しみを描いています。新興宗教の話が挿入され、子どもの誕生を通して、聖と性の対比が浮き彫りにされます。過去の作品と比べると、かなり大胆なテーマにチャレンジしていますね?
榊英雄(以下、榊):これまで笑いあり涙ありのウェルメイドな作品を追求してきましたが、今回は振り幅の激しい作品を手がけたいと思いました。40歳を過ぎた頃、自分の中にも勇介が抱えるザワザワ感があることに気づき、それを払拭したい気持ちがよぎりました。
————原作のどんなところ惹かれたのですか?
榊:生きていくことに答えはない。人間は愚かで哀しい。だからこそ、愛おしくもある。そうした世界観に心惹かれました。
————五島列島のロケが大変素晴らしい効果を発揮しています。南国の強い日差しが欲望を露わにし、海は人間の往く末を見守ります。土地の言葉には独特の響きがあって、どこか神話めいた雰囲気を醸しています。
榊:原作はただの漁師町という設定ですが、映画化するに当たって、真っ先に思い浮かべたのは故郷の五島でした。五島で撮ることは、自分をさらけだすことでもある。18歳まで暮らしたので、僕はこの町の酸いも甘いも知っています。人々の暮らしや男女の営み、人は生きて死ぬという事実を目の当たりにしてきたので、作品の世界観を表現できる場所はここしかないと思いました。
————五島は隠れキリシタンの里であり、西洋風の教会がたくさん残っています。信仰の風土であることも、物語にふさわしいと感じたのではありませんか?
榊:隠れキリシタンと物語に登場する新興宗教に関連はありません。ただし原作には、人間を鳥瞰して眺める視線————「神の視点」が一貫して感じられます。「捨てがたき」には、神は人間を見捨てないという意味もある。
映画では、こうしたヴィジョンを表現しようと、岬に立つ聖母像をシンボリックに提示しました。僕は隠れキリシタンの家系ではありませんが、そうした意味では風土に多大なインスピレーションを受けた作品です。
————冒頭のシークエンスは鮮烈ですね。映画全体を凝縮して、衝撃に満ちています。
榊:導入部は編集のとき、七転八倒しながら編みだしました。脚本では台詞があるだけで、場面構成は漠然としていました。シークエンスの終わりに勇介のカットを入れたらいいと気づいたのは、大詰めの段階です。おかげでエモーショナルになり、全体の統一感も生まれました。
————映画では省略していますが、原作には2人の過去がひんぱんに登場します。
榊:今の勇介と京子を見せることに専念し、その中でどんな生い立ちなのか示そうとしました。
————勇介の過去は特に悲惨で、子どもの頃、母に逃げられ、父を殺そうとした経緯があります。なぜ、こんな人間になったのかを示す重要な場面であり、回想シーンで示すことも考えられたはずですが?
榊:子役を用意してこんな過去があったと説明するのは、この映画ではわざとらしい。大森南朋の芝居で伝わるはずだと思い、酔っぱらいに絡まれ無人の生家を訪ねる場面に象徴させました。
————映画の主人公は、原作以上に強烈な個性を放っています。勇介は内気な部分が退けられ、無口でトゲのある男として登場します。
榊:勇介は、大森南朋さんの精神と肉体を通過することで、強固なキャラクターになると確信していました。劣等感の部分も内向的ではなく、ギラギラと放出されるようにしたかった。大森さんのおかげで原作者も太鼓判を押す人物像ができたと信じています。
————京子のキャラクターを顔にアザがある人物に変更していますね。
榊:三輪ひとみさんが美人なので、どこかで負荷を与えようとしました。挑戦でしたがそうすることで、他者に対する関係性とか、容姿に対する感覚を原作に近づけることができたと思います。
————髪型を工夫したり、メガネをかけさせたりして、コンプレックスを引き出すこともできたはずですが?
榊:僕が生まれる少し前に、世間を揺るがす大事件が五島で起きました。カネミ油症事件(1968)です。精製上のミスで劇薬の混ざった食用油が大量販売され、多くの家庭がこれを使用していたのです。斑点やアザのある人が五島に多いのはそのためです。母親の体内に蓄積された毒素が遺伝するため、僕らの世代にも症状のある人がいるくらいです。
母がカネミ油を使わなかったので僕は無事でしたが、遺伝によって発症した幼馴染みが実際におり、子どもの頃、母によく「優しくしてあげなさい」と諭されました。京子を事件の直接的な被害者として描く意図はありませんでしたが、五島で撮ることのリアリティを考えた結果、思い切った変更を加えました。
————勇介と京子は愛のない身体の関係で、京子がひとり宗教的な隣人愛を抱いているに過ぎません。ところが、妊娠をきっかけに勇介の心が大きく揺れます。墓地で勇介が家族の存在を問う場面は、すべてを受け容れるような平穏さに満ちています。
榊:実は僕自身、今は亡き父に、家族を持って良かったのかと問いたい気持ちがあります。祖父が蒸発し、父は父性を知らずに育ちました。長らく音信不通だった祖父は、死ぬ間際に父に手紙を寄越します。金を無心する内容で、父は深く傷ついたと思います。ある日通知が来て、祖父は死んで無縁仏に納められたとありました。生前に仲直りできればよかったけれど、無縁仏への墓参りが祖父と父の再会になってしまった。
やがて父は、祖父の人生をなぞるように家出し、放浪生活をおくった末に亡くなります。僕も父性を学ぶ機会に恵まれなかった。子どもが生まれて僕の誕生を父はどう思ったのか知りたい気持ちもあって、あの場面をつくりました。

————海に臨む墓地は寂寥感が漂っていますね。
榊:赤島という離島の墓所が気に入り、そこで撮影しました。赤島にはかつて500人ほどの島民がいましたが、漁業が衰退し、今は20人程度が住んでいるだけです。多くの住人が引っ越したため無縁仏と化した墓地があります。前方後円墳みたいなかたちの土地に墓が立ち並び、ぼうぼう草とテッポウユリに覆われている。素晴らしい場所で、神を前にしたような敬虔な気持ちが湧いてきました。
————子どもが生まれる場面は、音と映像のモンタージュだけで構成されています。聖と性の対比がまざまざと浮かび上がり、映画作家・榊英雄の誕生を伝えるすばらしい場面です。
榊:脚本の段階からいろんな想を練っていて、セックスして子どもが生まれる営みを、「神の視点」を通して描こうとしました。音を入れるうちにセックスと出産が意想外なかたちでミクスチャーでき、自分でも会心の場面になったと思います。
————中盤では、周辺人物の三角関係が畳みかけるように展開されます。美保純さんが事件の意味を問う重要な役を演じ、田口トモロヲさん、内田慈さん、滝藤賢一さんが強い印象を刻みつけます。出番が少ない俳優でも、確かな演技を引き出しているところに俳優出身である監督の手腕を感じます。
榊:長年役者で飯を食ってきたので、経験上の勘から油断している時はすぐわかります。納得のいかない時は何度も粘りました。たまに演出していて、身体の疼く瞬間があって、カントクなのに役者魂が抜けてないと悲しくなりました(苦笑)。
役者に必要なのは、目つきや話し方を始めとする役のイメージを掴むことです。そのために最初に、演出上のイメージを役者に伝えます。次に原作を読んでもらい、役の精神的背景を理解してもらいました。
現場では基本的な部分は役者に任せているので、こう演じてほしいとゴリ押しすることはありません。解釈で思い悩んでいる時は話し合い、建設的に役を掴んでもらうよう努めました。唯一の例外がセックス・シーンで、緊張するし照れもあると思うので、僕がまず演じて段取りを理解してもらいました。
————10年後の勇介と京子を描くパートでは、生まれた子どもとの関係で2人のその後が語られます。原作にはない、京子と子どもの場面が新たに付け加えられ、男女の愛だけでなく親子の愛も見据えています。
榊:原作では後半、勇介を捨てた母親が弟を連れて現れ、前世の因縁は未来永劫続くことが示唆されますが、勇介と京子、子どもの関係を掘り下げて、その境遇を詳らかにしようと考えました。
子はかすがいと言いますが、セックスの欲望を捨てられる人間はそういない。大切にしていた信条を忘れて快楽を貪る京子と、母親の純粋な愛情を求める子どもの姿を対比させ、人間が持つ業の深さを抉ろうとしました。
————終盤の夫婦の修羅場は、押し殺していた感情がほとばしる大切な場面です。演出的にも苦労されたのではありませんか?
榊:感情面で狙い所は見えていましたが、芝居が見えず苦労しました。思い定めた高みに到達できなければ、カメラを回しても意味がない。僕にとっても、主役の2人にとっても勝負でした。結局、納得できるテイクを撮るために24時間かかりました。
最初は長丁場になると思わなかったけど、途中でこれは駄目だと観念し、「ゴメン。1時間眠らせてくれ」と休憩しました。僕も消耗したけど、大森さんも三輪さんも大変だったと思います。
————原作ではその後も話が続き、人間は煩悩から逃れられないことを示して終わります。映画では、この場面にすべてを集約させ、愛への渇望、生命への果てなき問いに物語が昇華されています。
榊:家族が互いの存在をつなぎとめるのか否か、ギリギリのところで見せようとしました。ラストの大森南朋の顔にすべてを託したので、そこで感じたことが真実です。勇介が最後に振り返ったのは何かが聞こえた証しですが、誰のどんな声が聞こえたのかは分かりません。これは答えがあって終わりという、ありきたりな映画ではないからです。
————人間を救いがたい存在として描きながらも、どこか優しい気持ちになれる作品ですね。
榊:家族が居ても人間は孤独であり、ひとりで生きて死んでゆく。そんな宿業を仮借のない目で見つめました。それでも優しさが感じられるとしたらジョージ秋山先生のおかげです。
今後も、出会いとインスピレーションに委ねていろんな題材に挑戦するつもりですが、折に触れて自分が立ち返る場所はここなんだと思っています。この先どんなふうに生きればいいのか、覚悟を込めました。その意味で、これは僕の決意表明となる作品です。
2013年9月19日(木)六本木アカデミーヒルズ49
(インタビュー取材・構成:赤塚成人)
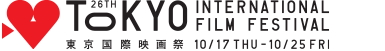







 Check
Check
