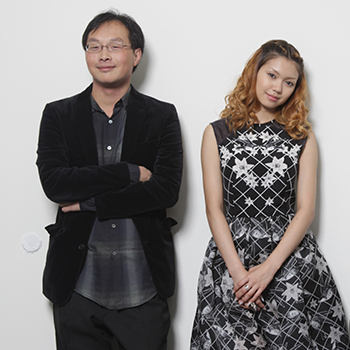
『ほとりの朔子』
『歓待』(2010)は、第23回東京国際映画祭〈日本映画・ある視点〉作品賞に輝き、のちに第15回プチョン国際ファンタスティック映画祭でNETPAC賞を受賞。個人賞でも、第3回TAMA映画賞の最優秀新進監督賞(深田晃司)と最優秀新進男優賞(古舘寛治)、さらには、第33回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、おおさかシネマフェスティバル2012新人女優賞(共に杉野希妃)を獲得するなど、国内外のフィルム・サーキットで大いに注目を集めた。
再び、杉野希妃プロデュース・出演で臨む深田晃司監督の最新作は、18歳女子の淡い青春物語。大学受験に失敗した朔子(さくこ)が高校生の亀田孝史と出会い、別れるまでを夏のまばゆい光の中に描く。朔子役の二階堂ふみが飾り気のない魅力を振りまき、相手役の太賀が爽やかな演技を披露。鶴田真由がオトナの事情を担う役で華を添え、青年団の常連キャストが脇を固める期待の一作だ。
1950年代末から60年代にかけて、フランスで新進の映画作家たちが台頭し、自然光と手持ちカメラを用いて作品を撮り始め、撮影所から映画を解き放った。33歳の監督は、こうしたヌーヴェルヴァーグの営みを現代に継承しようと試みる。日本のヌーヴェルヴァーグが政治や人間存在にメスを入れる中で見落としてきた系譜————トリュフォーの初期短編やロメールの「喜劇と格言劇」に見られる味わいを表現しようとするのだ。
果敢な野心が功を奏し、『ほとりの朔子』はひと夏の出来事を描きながら、現代日本のデリケートな問題を提示する成熟した作品となっている。コンペティション部門に初選出された監督と、自然体の演技で多感な青春像を抽きだした女優に作品の見所を聞いてみた。
————『歓待』がブラックな味わいの群像喜劇だとすれば、『ほとりの朔子』は、緩やかな人間関係が織りなす恋愛劇であり、自然と笑みのこぼれる作品になっています。
深田晃司監督(以下、深田):もともと僕はこうしたテイストの作品が多く、『歓待』のようなワンシチュエーションを追求したドラマは、むしろ例外に属します。登場人物の出し入れ————誰と誰がいつどこで出会い、話し、別れていくか———を洗練させて、何かを伝えたい。その思いに変わりはないにせよ、『ほとりの朔子』ではこれまでよりも、生身の人間の息づかいを尊重しようと心懸けました。
————杉野希妃さんと古舘寛治さんが『歓待』と似た役どころで登場するのも、笑いを誘います。古舘さんはケッタイな隣人だけど、どこか憎めない。杉野さんは女子大生の役ですが、またも本音を吐く存在でビンタする場面があってドキドキしました(笑)。今回は、身近に居そうな人物を演じているぶん、それぞれ実際のキャラクターを彷彿させます。
深田:2人とも個性を生かして、うまく演じてくれました(笑)。僕は、杉野さんがプロデューサーとして苦労されているのをよく知っています。そうした姿を間近で見ているので、女優としては、どこか吹っ切れた役を演じてほしい気持ちがあります。感情を炸裂させる瞬間の杉野さんは、もう惚れぼれするほど格好いい。本当に輝いていますからね。
————海と山に囲まれた土地が舞台で、夏の光あふれるロケーションが目に焼きつきます。描かれる土地に憧れる観客も多いと思いますが、登場する地名はありそうでなさそうな名称ですが?
深田:その通りです(笑)。主なロケ地は三浦半島と木更津で、一部都内でも撮影を行いました。いずれも最高のロケ地でしたが、普遍的な青春物語にしたかったので、映画に登場する地名はすべて架空にしました。
————いま最も輝いている女優、二階堂ふみさんの出演はどんなふうに決まったのでしょう?
深田:二階堂さんには、第3回TAMA映画賞の授賞式で初めてお会いしました。挨拶した時の印象が凄く新鮮で、エネルギッシュで若々しいのに、クールな一面もあって、自分なりの考えをしっかり持っている。相反する個性がひとつの身体に共存しているスリリングな部分に惹かれました。
大人と子どもの間の宙ぶらんな時期にあって、どちらの側にも感情が揺れてしまう。そんな不定形な時間を描くにはピッタリで、二階堂さんを想定して脚本を書き進めました。タイトルの「ほとり」は、海と山に囲まれた土地を指しますが、大人と子どもの中間で、そのどちらでもないという意味も込められています。
————二階堂さんは脚本を読んで如何でしたか?
二階堂ふみ(以下、二階堂):深田監督の作品は『歓待』を観ていて、その時からずっと一緒に仕事がしたかったので、正式にオファーが来た時は嬉しかったです。
脚本を読んで思ったのは、男っ気のない役なので、変に華々しくしたくないということでした。高校を卒業したての若い役柄だから演技らしい演技はなしで、少女と女性の間のきれいな感じを出そうと努めました。少女でもなく、だからといって大人の女性とも違う麗しさ。日本映画の昔の女優が持っていた清らかさを出せたらいいと思いました。
————朔子が外出する場面では、ユニークな身体感覚が強調されています。「海だあ」と言って両腕をぶらぶらさせたり、レストランを出てジグザグに歩く場面などは、即興的に演出されたのですか?
深田:即興演出というよりも、二階堂さんの自然な振る舞いです(笑)。
二階堂:動きに関して監督の指導はなく、全部OKだったので、ふだん自分が歩いている時の感じでやりました。演技じゃなくて素のままです(笑)。

————日記風に物語が展開されるため、二階堂さんが日替わりで着こなすファッションにも注目が集まりそうですね。チューブトップにデニムのショートパンツを合わせたり、大人びたストライプのワンピースを着たり、チャーミングな水着姿まで登場します。ファッションに併せて、髪をシニヨンにしたり、ポニーテールにしているのも魅力的です。
二階堂:等身大の役で、いろんな洋服を着て演じられたので、気持ちよかったです(笑)。私は衣装さんが選ぶ服に、たまに違和感を覚えることがあって、現実にはいない少女を大人の思い込みでイメージしているだけという印象を受けます。でも今回は、担当の荒木里江さんがとても素敵な方で、18歳の多感な年頃に合った服をたくさん見つけてくれました。
朔子は大人っぽかったり子どもぽかったりするので、「赤のワンピースかわいいね」「水色もひとつに絞りたくない」と相談しながら、その時々のイメージを作っていきました。着心地の良い服ばかりで、服に併せて髪型も変えてみました。
————二階堂さんもさることながら、鶴田真由さんや杉野希妃さんも、ファッショナブルで雰囲気があります。
深田:夏を舞台にした作品だから、衣装はカラフルにしようと決めていました。ノースリーブで二の腕を出したり、ショートパンツで太ももを露出しているのは、自然に素肌を晒している感じにしたかったからです。エリック・ロメール監督の夏を描いた作品のように、清潔感ある健康的な色気を出そうとしました。
————本作では、『歓待』以上に複雑な家族関係が描かれ、観ているうちに、思わずニンマリしてしまう事実が明かされます。大人の恋愛事情と朔子が抱くほのかな恋心のコントラストも見事です。技ありの脚本ですが、先に登場人物をきめて書き始めるのですか。それとも部分的な人間関係を書くうちに、全体を構想されるのでしょうか。
深田:両方の作業を往来し、書き上げるまでの間、かなり細かい部分まで調整していきます。今回は朔子が叔母に連れられて、海と山を見晴らす土地にやってくるという枠組みだけきめてありました。ラストの朔子の顔が一番豊かに映えるにはどうすべきか。そこに向けて、いかに面白くできるかが勝負でした。次々に場面を書いて、連想ゲームのように膨らませていきました。
————鶴田真由さん演じる叔母をインドネシアの研究者にしたのは、どんな理由からでしょう?
深田:大人と子どもの狭間で揺れている朔子が、ちょっぴり世界に目を向ける。そうした物語上の導線がほしくて、国際的な研究者という役柄にしました。脚本を書く前年、仕事でインドネシアのアチェに初めて行き、強烈な印象を受けたことが決め手となりました。
————ちょっと前に言ったことに反応したり、意味を取り違えて修正したりと、台詞のやりとりにも妙味があります。また「なぜ外国の研究をするのか」という問いに対して説かれる道理も真っ当です。台詞にも独特の美学が感じられますが?
深田:ふだん映画を観る時は気になりませんが、自分で脚本を書く時は、名台詞を書かないよう気をつけています。みんなたくさん喋っているのに大事なことは何も言わない。そういうのが好みです(笑)。
テクニカルな作業として念頭にあるのは、ノイズを増やすことです。人はいつも理路整然と喋っているわけではない。でも、脚本家はストーリー進行を優先させるあまり、ついノイズを排除しがちです。そうすると意味はよく通るけど、日常のおしゃべりからは遠ざかってしまう。そうならないためにも、あえて日常会話の要素を残すようにしています。

————ハリウッド流ストーリー・テリングではなく、実際の会話に近い感覚で脚本を仕上げるのは、さぞ忍耐を要するのではありませんか?
深田:忍耐ではなく楽しんで書いています(笑)。人間は毎日、関係性の中で言葉を作っています。周囲との関係や環境に応じて、喋らされているとも言える。関係性を無視して本音を切りだすことはない。あったとしたらそれは修羅場です。
僕は人生の修羅場はほんの2%程度であり、残りの98%は平凡な毎日だと考えています。平凡な毎日を重ねることで人生は豊かになる。だから映画も、ありきたりな状況をどれだけ面白く描けるかで決まると思っています。
まず初めに登場人物ありきで、関係性から生まれる意味のないおしゃべりで、映画を成立させたい。その中に綻びがあって本音が透けて見えたらいい。そうした映画づくりを目指しています。
————台詞の多い脚本なので、演じる側は大変だったのではありませんか?
二階堂:急に追加の台詞が来たりする部分では、確かにそうでした(笑)。
深田:ギリギリまで直すのが好きなもので(苦笑)。
二階堂:現場でいきなり長い台詞が来て、「マジかよ!」みたいな(笑)。それで昼休みに、鶴田さんと台詞合わせをしました。でも追加があっても、台詞がすんなり入ってくるのは、自分が日常的にしている会話と言葉の鮮度が近いからでしょうね。
お芝居していると、こういうこと言えないなという台詞があって、それはそれで楽しい。でもこんなふうに、自然とつらつら言葉が出てくることはあまりない。現場でも素敵だなあと思いながら演じていました。
————ホテルと反原発集会の挿話にはとぼけた味があります。これらは孝史の成長を示すエピソードとして、マイノリティの視点からシニカルに描かれるところに特色があります。
深田:いま映画を作ろうとすれば、東北や福島で起きたこととどう向き合うべきか考えざるを得ません。賛成とか反対を唱えるだけでは意味がない。否応なくそうした状況に巻き込まれた人々と、どう向き合えばよいのかが大切になります。
僕個人は反原発の立場でデモにも参加しています。でも自分の立場を直接反映させるだけでなく、信じているものに疑いの目を向けてみるのも、映画の豊かさだと思います。被災された方々にもいろんな考えの人間がいるのは当然であり、多様性に組することで、埋もれてしまった声を掬いとりたいと思ったのです。
————朔子と孝史はひょんなことから家出し、街道沿いの店で大道芸のパフォーマンスを見ます。とても印象的な場面ですね?
深田:映画の中の出来事は、現実の世界と同じで、最初に意味があるのではありません。見る人が何かを感じることで、意味らしき何かが生まれます。
パフォーマンスを見た朔子と孝史、周囲の客は魅了されますが、それぞれが違う感動を受け取ったのかもしれない。そんな余白を残した場面です。
————二階堂さんはあの場面を演じていて、どんな気持ちになりましたか?
二階堂:とても切ない気持ちになったことを覚えています。
————将来の夢を聞かれて、朔子は言葉を茶化します。ホンネはどうなんでしょう?
二階堂:何も考えてないんだろうと思っていました。とりあえず、「ヒミツ」って言っておこうと(笑)。
深田:いい答えだね。監督だから、役者だからって、すべてを知っているわけではない。それは朔子だけが知っていることで、彼女の性格からしてたぶん誰にも話さないはずです(笑)。
2013年9月19日(木)六本木アカデミーヒルズ49
(インタビュー取材・構成:赤塚成人)
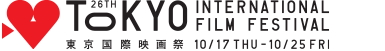







 Check
Check
