東京国際映画祭事務局 作品チーム・アドバイザー 森岡道夫さんロングインタビュー
第1回 東宝プロデューサーを経て映画祭に入るまで
東京国際映画祭事務局に長く在籍され、映画祭の「生き字引」とも言える森岡道夫氏。今回、第25回の終了を契機に森岡さんに話を伺い、第26回以降の新たなスタートに立ったこれからの東京国際映画祭に役立つ示唆をいただくためにも、インタビューをお願いしました。
現場で働く上で、ヒントとなる事柄も登場すると思います。
連載は今のところ、10回ほどを予定しておりますが、まだ取材途中ではあるので、内容によっては連載が多少増えるかもしれません。
まず、この第1回では、森岡さんが映画祭に関わる前史とでも言うべきお話を伺いました。プロデューサーとして映画に深くかかわってきた経緯や、映画をどう考えていらっしゃるのか、森岡さんの映画論も乞うご期待!

──森岡さんは、もともと映画少年だったのでしょうか?
森岡道夫(以下、森岡):教師をしていた両親が映画好きで、赤ん坊の頃から、僕を映画館に連れて行ってくれました。生まれは佐賀ですが、家のすぐの近くに映画館があって、映画を観る習慣が身に付いていたのです。物心ついた頃に観て記憶にあるのは『エノケンのちゃっきり金太』。あとドイツ映画の『會議は踊る』を観て、リリアン・ハーヴェイというきれいな女優さんが大写しになって、うっとりしたのを憶えています。そんなわけで、映画にも興味がありましたが、もともとはラジオドラマの方が好きでしたね。
──当時、ラジオドラマは相当盛んだったそうですね。
森岡:テレビのない時代でしたから、単発のラジオドラマをよく聞いていました。映画には実像が出てきますよね。いくらうまく演じても、所詮、この人は高倉健だとなる(笑)。ところがラジオドラマは自分のイメージで全体を思い描ける。ピュアなところに惹かれていました。
──就職するまで佐賀で過ごしたのですか?
森岡:幼少の頃だけで、育ったのは岡山です。地元の旧制高校に入って、そのまま新制大学の第一期生になりました。大学の頃は学校へ行くよりも、映画館に通う時間の方が長いくらい映画に夢中でした。当時、岡山駅前には5件ほど映画館があって、盛り場にもまた幾つもある。市内だけで20件もの映画館がありました。戦時中は外国映画の輸入が規制されていたけれど、戦後、雪崩のように名作が入ってきた。もちろん新作も観ましたが、旧作をまとめて上映してくれる名画座には足繁く通いました。戦前のヨーロッパの名作は、ほとんど岡山の名画座で観ました。
──当時観たもので、いまも思い出に残っている作品はありますか?
森岡:僕は子どもの頃からドイツ映画が好きでしたから、ヴィリ・フォルスト監督の『マヅルカ』や『たそがれの維納(ウィーン)』には感激しました。また、フランス映画もよく観ていて、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の『商船テナシチー』『にんじん』『望郷』や、マルセル・カルネ監督の『霧の波止場』などは、とりわけ印象に残っています。文学青年だったせいか、明るく楽しいアメリカ映画よりも、ヨーロッパの作品に興味がありました。
──上京するのは、東宝へ就職したのがきっかけですか?
森岡:就職試験ではまずNHKを受けましたが、岡山は広島中央放送局管内です。東京に出たい一心で東宝を受けたら運よく受かって、それで上京しました。東宝では文芸部を志望しましたが、新入社員は配属できないと言われて、最初の一年は経理をやり、のちに人事課に移動しました。幸いだったのは、これが撮影所の人事課だったことです。撮影所勤めだから、ときどき職場を抜け出してはステージ見学に行きました(笑)。
──撮影所というのは成城の砧撮影所ですね。かつて東宝が自社作品を作る場でしたが、1971年以降は貸しスタジオとして開放されています。2011年に8年越しの改造計画が終了しますが、入口には名物だった噴水の跡が今も残っています。
森岡:思い出に残るエピソードがあります。僕がたまたま通りかかると、演技担当の男性職員がランニングシャツを着た小さな子どもと一緒にいました。トイレに行くからちょっと頼むと言われて、その男の子が元気に暴れ回るのを見ていました。やがて職員は帰ってくると、その子をステージに連れて行きました。この時の子役が、五代目中村勘九郎(2012年12月5日に死去した十八代目中村勘三郎)だったのです。
当時、5~6歳でしたか。『アッちゃんのベビーギャング』(1961・杉江敏男監督)という映画の撮影でした。出番じゃなかったからステージの外にいたんですね。そんなふうに人事という堅苦しい仕事をしながらも、撮影所の雰囲気を味わっていました。その後、念願叶って文芸部に配属されて、映画製作に携わるようになります。
──東宝ではどんな作品を製作されたのですか?
森岡:プロデュースして、最初に自分の名前を出したのは、『父ちゃんのポーが聞える』(1971)です。監督は石田勝心という当時の若手で、能登半島でロケをしました。
──これはアイドル時代の吉沢京子がハンチントン病の少女を演じた感動作です。文部省推薦映画となって、のちに全国の小中学校でも上映されました。インターネットで、「学校の体育館で観て涙が止まらなかった」という書き込みをいまも目にします。
森岡:当時、文部大臣賞を受賞したので、その流れで学校でも上映されたのでしょうね。僕が製作したたった1本の難病もので、父親がSLの機関士で、病気で入院している少女の近くを走るとき、汽車の警笛を鳴らす。DVD化されてない作品ですが、そんなふうに憶えていてくれる人がいるのは嬉しいですね。
──その後は、どんな映画に関わったのでしょう。
森岡:大作では、山本薩夫監督の『華麗なる一族』(1974)、岡本喜八監督・倉本聰脚本の『ブルークリスマス』(1978)、森谷司郎監督の『海峡』(1982)を手がけました。変わったところでは、海外ロケした作品が2本あります。スイスを中心にヨーロッパ・ロケしたメロドラマ『神様なぜ愛にも国境があるの』(1979・吉松安弘監督)と、ネパールでロケした栗原小巻主演作『菩提樹(ピパル)の丘』(1985・戸田康貴監督)です。

──キネマ旬報の昭和49年度ベストテンでは、『華麗なる一族』が第3位に輝いています。キネ旬では芸苑社の製作となっていますが?
森岡:製作は芸苑社ですが実質的に東宝の作品です。もともと1950年代から60年代までの量産時代は、東宝本体が製作した作品だけでは上映本数が足りず、東京映画と宝塚映画でも東宝の作品を作っていました。
量産時代が終わると、東宝は他社に先駆けて製作部門を切り離し、配給・興行に特化します。そして製作は、新たに設立された下請けの会社が行うことになりました。芸苑社はそのひとつで、東京映画にいた佐藤一郎が設立した製作プロです。僕は東宝の社員として、芸苑社の仕事に関わり、その後、東宝映画に出向することになりました。
──『海峡』は東宝創立50周年記念作でした。
森岡:50周年を記念して5本の作品が製作されましたが、そのうちの1本です。これが東宝で手がけた最後の作品です。青函トンネル開通に到る物語で、老トンネル掘りに森繁久彌、国鉄技術者に高倉健、洞爺丸事件で両親を失った青年技師に三浦友和という、3世代の男の生き様を描いています。女優では吉永小百合が華を添えています。
──製作された映画の中で、今もお気に入りのものはありますか?
森岡:個人的に好きなのは、市川崑監督が撮った『吾輩は猫である』(1975)。それから、青島幸男が主人公を演じた『告訴せず』(1975・堀川弘通監督)です。
──青島幸男というと、いじわるばあさんのイメージが強いですね(笑)。
森岡:これは松本清張の小説の映画化で、選挙資金を持ち逃げする男の話です。最後に窮地に追い込まれるけど、持ち逃げしたカネのことだから告訴できずに悪戦苦闘する。
──市川崑監督は横溝正史シリーズが有名ですが、『破戒』(島崎藤村原作)、『炎上』(三島由紀夫の『金閣寺』が原作)といった純文学ものも多く手がけていて、夏目漱石では『こころ』も作っていますよね。
森岡:『吾輩は猫である』も大先輩の佐藤一郎と一緒に作った作品です。僕ら若手プロデューサーが監督を選ぶときは、東宝専属の若い監督を人選するのがつねでしたが、佐藤一郎は大物でしたから、「今度はコンちゃんにしようか」、「薩ちゃんに頼むかな」と、自由に選ぶことができました。
──プロデューサーとして、独自に試みられたことはありますか。
森岡:映画製作の上で、音楽は重要だと思っていましたので、少し目先を変えてみようと、映画音楽の専門家ではない人に音楽を頼んだりしました。例えば、『海峡』では南こうせつさんに頼みましたね。それから『神様なぜ愛にも国境があるの』では、ゴダイゴのミッキー吉野に任せました。『ブルークリスマス』の主題歌はCharです。若いミュージシャンは風体はすごいけど純粋な人が多い。人柄に惚れ込んで結構、起用しましたね。
──1971年から10年以上、映画製作に関わってこられましたが、企画を立てる際、どんなご苦労をされましたか。
森岡:映画の素材はホン探しに始まるから、片っ端から本屋を回っていました。でもそれだけでは駄目で、出版社に行って、発売前の新刊の情報を仕入れないといけない。佐藤一郎や藤本真澄といった大プロデューサーは、出版社はおろか作者とも仲良くなって、映画の原作を書いてくれと頼んでいました。
僕が関わった作品では『海峡』がこのやりかたで、まず原作(ドキュメンタリー作家の岩川隆が執筆)を書いてもらうところから企画をスタートさせ、文藝春秋で刊行される本と同時進行で映画を作りました。完成まで3年越しでした。映画の企画としては、知名度のある原作がいちばん楽だけれど、新聞のコラムで見たちょっといい話とか、素材はあちこちに転がっています。最近は活字だけでなくインターネットでも読むことができるから、昔より進歩しているでしょうね。

──多忙な時期に、作品をかけもちしたことはありますか?
森岡:ちょうど『海峡』が終わった頃に、フリーで『転校生』(1982・大林宣彦監督)をやっていて、もう1本、『菩提樹(ピパル)の丘』(完成は1985年)をネパールで撮影していました。その後も、大林監督の作品が同時進行することになって、撮影所に『四月の魚』と『彼のオートバイ、彼女の島』(いずれも1986)の各セットを作って、行き来しながら撮影したことがあります。
──大林監督とはどのように出会ったのですか?
森岡:剣持亘という脚本家がいて、とても親しくしていました。彼がある日、電話をかけてきて、面白い原作があるからと持ってきた。それが山中恒の児童文学『おれがあいつであいつがおれで』(後に映画『転校生』となる)でした。読んでみるとなかなか面白くて、監督は誰がいいかと聞くと、彼は、大林宣彦監督の名前を挙げました。私も適任者ではないかと感じたので大林さんに頼むことにしました。
──大林監督は当時、何を作っていたのでしょう。
森岡:薬師丸ひろ子主演の『ねらわれた学園』(1981)を撮り終えた頃でした。尾道の向かいにある島の別荘にいた大林さんのもとに、剣持さんが話に行くと、大変乗り気でやってくれることになった。でも男と女が入れ替わる話をどうやるのか、最初はかなり悩みましたね。ぬいぐるみを着せるのか、声だけ吹き替えるのか。結局、本物で行こうとなって、尾美としのりと小林聡美に演じてもらいました。
──『転校生』ではATGの佐々木史朗氏も製作に名を連ねています。
森岡:製作母体のサンリオが撮影に入る一週間前に降りてしまい、急遽、佐々木さんに会いに行きました。サンリオが降りたと大林さんに伝えると、辞めるにはあまりに惜しい企画だと言われ、資金協力を要請したのです。そうしたら、佐々木さんも乗り気になって、日本テレビと松竹に話をつけてくれました。それで佐々木さんが製作総指揮。製作が日本テレビ=ATGで配給が松竹と決まりました。口コミで評判が広まって、松竹では1年間も上映してくれました。
──昭和57年のキネマ旬報ベストテンには、ATGが製作に関わった映画が3本も入っています。『転校生』(第3位)、『TATOO〈刺青〉あり』(第6位)、『怪異談 生きてゐる小平次』(第10位)です。
森岡:当時、ATGが商業的な作品を多く手がけたので、東宝ではライバル出現と囁かれていました(笑)。作品が好評だったことから、その後、九州の柳川で撮った『廃市』(1984)から『はるか、ノスタルジィ』(1993)まで、8本の大林作品で製作に就きました。
──フリーになって製作した作品でも、砧撮影所を使いましたか?
森岡:48歳でフリーになってからは、製作費を抑えるため、よく日活スタジオを借りてやってました。『四月の魚』と『彼のオートバイ、彼女の島』を同時進行で撮ったときも、日活スタジオです。
──この頃、大林監督は『時をかける少女』(1983)、『天国にいちばん近い島』(1984)など、角川春樹さんが製作した作品も撮っています。森岡さんは、角川映画の作品にも関与されたのですか?
森岡:『彼のオートバイ、彼女の島』(1986)では角川さんの下で製作に関わりました。
──原田知世の実姉である原田貴和子が主演した作品ですね。
森岡:相手役は、のちに「ミナミの帝王」シリーズでスターになる竹内力です。竹内力は九州で三和銀行の社員をしていましたが、役者になりたいと一念発起して、オートバイで東京に出て来ました。そして、三浦友和のいる大手芸能事務所に入ったばかりでした。九州からオートバイで上京した男がいると事務所から紹介され、大林監督に会わせるとすっかり気に入って、「この映画に出るのはキミの運命だ」と(笑)。それで主役に抜擢されたのです。
──映画プロデューサーは実際にはどんな仕事をされるのでしょう。先ほど、企画の話が出ましたが、その他にも山のような仕事がありそうです。
森岡:一般の方には、プロデューサーと監督の違いがわかりにくいみたいですね。監督はいわば芸術家。プロデューサーは事業家です。お金集め、脚本づくり、監督やキャストの選定、製作進行管理、配給・興行まで面倒を見て、出資者に収支報告するまで受け持たねばならない。その全行程を担当するのがプロデューサーです。だから、企業のなかのプロデューサーは本来ならば企画者ですが、東宝では森岩雄がプロデューサー制度を導入したおかげで、自分の企画が実現するとプロデューサーを名乗ることができました。
他の会社では、製作に社長の名前を出し、僕らのような立場は「企画」と表記されるのが一般的です。たとえば、大映なら「製作永田雅一、企画藤井浩明」。東映も同じで「製作大川博、企画俊藤浩滋」でした。いずれにしても、監督は芸術家で、時に闘わなければならない相手です。その意味では切磋琢磨が必要になります。
──ひと口にプロデューサーといっても、いろんな方がいますよね。
森岡:僕らのように大手で企画を経験して独立した人もいれば、現場の叩き上げでプロデューサーになった方もいます。撮影所に入って、製作現場を切り盛りしてきた専門家。これは僕らにはできない役回りを担ってきた方たちです。
──現場ではライン・プロデューサーと呼ばれる人もいます。
森岡:あれは製作主任です。ロケ先で撮影交渉をしたり、警察で道路使用許可を取ったり、弁当や車輌の手配をすべてこなす。その他にもさまざまな雑務があり、ひとりでこなすのは困難なので助手となる製作補が必要になります。
──最近ではプロデューサーとして、複数の方の名前がクレジットされることが多いですね。
森岡:組む相手によっては、協同プロデューサーの肩書きを与える場合もあります。かつては企画出身、現場出身、芸能プロ出身という3つのケースが主流でした。芸能プロ出身の代表例はホリプロの堀威夫さん。俳優を出演させて、製作に名を連ねました。最近は、お金を出資するだけのプロデューサーが多くなり、いまクレジットのトップに名前が出るのは、ほとんどがそうした方々ですね。
僕はいま映画祭の仕事のかたわら、プロデューサーとして新作を製作していますが、その場合でも、製作総指揮(エグゼクティブ・プロデューサー)としてオーナーの名前を最初に立てます。もともと、これは大映や東映が最初に社長名を出すのと同じ方式です。

──東宝からフリーになって活躍される一方で、森岡さんは30年近くのあいだ、東京国際映画祭に関わってきました。そもそも、映画祭に関わることになったきっかけは何でしょう。
森岡:1986年の秋、日本映画テレビプロデューサー協会の事務局長を務めているときに、第2回東京国際映画祭のヤングシネマ部門を協会で引き受けてほしいという要請が、映画祭サイドからありました。川口幹夫会長(当時NHK交響楽団理事長で、後に第16代日本放送協会会長)から、「映画畑出身の君が中心になってくれるなら、プロデューサー協会で引き受けようと思う」と、話を聞いたのです。もう井の中の蛙もいいところで、作ることが本業でも、配給・興行のことは何も知らない、まったく違う世界ですが興味があったものだから、大海に飛び込むような気持ちでお引き受けしました。
──このときの作品選定はどのようにされたのですか。
森岡:協会内で協力者を募ると、6名の方が手伝ってくれることになりました。テレビ界で有名な大山勝美、のちにアルゴ・ピクチャーズを設立する岡田裕、いまはアスミック・エースの特別顧問を務める原正人を始めとする方々です。地域ごとに担当を決めて作品選定を行い、僕はオセアニア地域を担当しました。大山さんは北欧担当で、フィンランドからアキ・カウリスマキの映画を持ってきてくれました。『パラダイスの夕暮れ』という僕の大好きな作品です。
第5回までプロデューサー協会主導で、ヤングシネマの作品選定を行いました。
──その後も長らく、映画祭の作品選定を担当されたのですか?
森岡:はい。最初は隔年開催ということもあり、プロデューサー協会の事務局長を兼任していましたが、第5回(1992)から映画祭に専従で就くようになりました。ずっとヤングシネマ部門の取りまとめ役を務め、コンペティションが一本化された後も、第15回(2002)まで作品選定に携わってきました。
プログラミング・ディレクター制度が導入された第16回からは、アドバイザーとしてさまざまな仕事をこなしています。
──森岡さんは戦前から映画を観続けて、製作現場から映画祭の作品選定まで、幅広く映画に関わってきました。日々進歩する映画に対してどんな感慨をお持ちでしょう。
森岡:リュミエール兄弟によって映画が発明されたのは1895年。日本に技術がもたらされたのは1897年のことです。そこから数えると、映画は今年で118歳。日本では116歳を迎えます。最初は無声でしたがトーキーになり、白黒からカラーに発展し、3Dに進化を遂げました。一方で、デジタル化が急速に進んで、フィルムで撮影して上映する環境が失われつつあります。だから技術面からすると、映画はこれからどこへ行くんだろうと思いますね。
いま僕は地域の仕事で、月に一回映画の話をしています。老若男女が聞きに来ますが、集まった人に聞くと世代によって映画観がそれぞれ違う。何歳で映画に接したかで、まるで違ってくるのです。それだけ映画は息が長いわけで、僕みたいに戦前から観ている人と、今の若い人では、映画の見方も変わっていることでしょう。でも、どれだけ世代による違いがあっても、映画は味わいながら観るものだと思います。技術が進歩したおかげで、目を瞠るような映像が体験できる反面、味わい深い作品が少なくなったのは残念ですね。

──有意義な話をありがとうございました。では次回から、各年度の映画祭を回顧しながらお話を伺いたいと思います。
取材 東京国際映画祭事務局宣伝広報制作チーム
インタビュー構成 赤塚成人
連載第2回へ→
連載第3回へ→
連載第4回へ→
連載第5回へ→
番外編1(連載第6回)へ→
連載第7回へ→
連載第8回へ→
連載第9回へ→
連載第10回へ→
連載第11回へ→
番外編2(連載第12(最終)回)へ→
連載終了のご挨拶:森岡道夫→
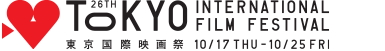







 Check
Check
