
公式インタビュー コンペティション 『レッド・ファミリー』
―イ・ジュヒョン(監督)、キム・ギドク(原案/エグゼクティブ・プロデューサー/編集)
「隣の芝生は何とやら」ではないが、北朝鮮のスパイチームは普通の仲良し家族を装い、韓国の住宅地で暮らしているその隣の家は、いつもいがみ合っているファミリー。ふたつの家族は次第に交流を深めるが…。来日した『レッド・ファミリー』のイ・ジュヒョン監督と、原案、エグゼクティブ・プロデューサー、編集のキム・ギドクさんにお話を伺いました。
――映画の中には本物の家族だけではなく、北朝鮮からのスパイチームによる偽装家族でも、しょっちゅう食事のシーンが登場しますね。あそこにはどんな思いを?
キム・ギドク:映画の序盤で出てくる食事のシーンは、北と南の対比をよく表していると思います。南の家族は、その辺の食堂で買えるようなインスタント食品を食べてケンカしている(笑)。北の偽装家族では、スープひとつで済ませられる非常に質素なもの。そして翌日になると、資本主義の南の家族は大切な食べ物を捨てているというところで、大きな対比になっている。しかし後半になるにつれて、隣のおばあさんが元々義理のお母さんに習ったという、ハンジョンドという北の地方の蒸し鶏を持って訪れます。その蒸し鶏こそがある意味、ふたつの家族をつなぐ道具なんですね。それまでは、両家には何らかの見えない線があったけれども、もうあの時点では、ふたつの家族を隔てる線はなくなっていた。だからこそ北の食事であるものを、両家族は一緒に食べられたのではないかと思います。
――家族、「カジョク」というのは、ペ・ヨンジュンさんがファンの人々をそう呼んで日本でも有名になりましたが、朝鮮語の「家族」は私たちが考える以上に強い絆があるのでしょうか。
イ・ジュヒョン監督:韓国には「かぞく」という単語もありますが、「しっく(食口)」という言葉もあります。文字通り「食べる口」という意味で、食卓も一緒に囲んで集まる人々を家族と同じ意味で使っているのです。それはやはり、「一緒に暮らしている人々」イコール「家族」なんですよ。
――キム・ギドクさんが書いた脚本を映画化するというのは、光栄であったと同時に、ものすごいプレッシャーだったのでは?
イ・ジュヒョン監督:そうですね。最初にキム・ギドク監督がシナリオを読ませてくださったときは、純粋にこれは自分が好きなストーリーだと思いました。ぜひ挑戦したいとも思いましたが、と同時にやはり不安でもあった。尊敬するキム・ギドク監督がくださったシナリオを、僕が演出することによってもしかしたら迷惑をかけてしまわないか。監督の顔に泥を塗ってしまうことにならないかと不安になって。しかしいざ撮影をスタートしてみたら、現場の俳優たちはもちろん、キム・ギドク監督やスタッフの方々からもエネルギーをもらって、とても感動しました。こうやってみんなで集まれば、本当にしっかりとした映画が作っていけるんだなと感じて、それを力に変えて臨めたように思えます。僕が作業の中心から逸れてしまいがちになると、その時々できちんとキム・ギドク監督がメッセージをちゃんと伝えていくべきなのだ、と本筋に正してくれたり。いろいろ忠告してもらえたのもとても大きな助けになりました。

――具体的には、どのような忠告を?
イ・ジュヒョン監督:キム・ギドク監督が常々言われているのは、「映画を作る時はその映画を観て、心臓の音がするような映画にしなくてはならない」。つまり、表現することとそれを抑制することとのバランスの取り方もあるし、時としては、あれを撮りたいこれも撮りたいと欲が出すぎることもあるけど、初心や本来描くべきことを忘れがちになってしまう時に、それを思い出すようにということですね。
――逆にキム・ギドクさんは、なぜイ・ジュヒョン監督なら、この映画化を託せると思ったのですか?
キム・ギドク:まずひとつ目としては、南北問題は韓国人なら誰もが知っているとても重要な問題だという点。記者会見でも言ったのですが、イ・ジュヒョン監督が作った短編のアニメーション映画を観た時に、この人は人間がどのようなときに苦痛を受けてどういうことに悩むのか、そしてどういう過程を経て成熟していくかがわかっている人だなと思いました。かつ、人間が受ける苦痛をきちんと理解して、人間が生きていくその価値というものは何かと常に悩んでいる。そんな監督なのだなということを感じたのです。それは、まさにこの『レッド・ファミリー』という映画がイデオロギーの中心にいて、そこに凝り固まってしまっている、閉ざされた人間たちの利己的な姿を描いていて、そこから人間性を取り戻そうとすることを描く映画なので、きっとこの監督ならばそれをきちんと表現できるだろうなと思ったのです。

――キム・ギドクさんにもうひとつ。あなたはいろんなタイプの映画を撮っていますが、例えば『嘆きのピエタ』と本作のように一見全く違った雰囲気であっても、血の繋がらない人間同士が狂おしいくらいに相手を求めて、本物の家族以上の絆を持ちたがるというところがつながっていますよね。
キム・ギドク:質問してくださった内容はとても正確にとらえてくださっていて、その質問にもう答が含まれていると思います。おっしゃったように血の繋がり、血縁がもちろん家族を表すのだけれど、実際にはその血縁がなくとも、人と人とは繋がることができる。一緒に過ごすことによってそこに縁というものができ、縁が続いていけば家族になりうると僕は思います。確かにそのことは『嘆きのピエタ』にも、今日の『レッド・ファミリー』にも描かれています。日本の是枝裕和監督の『そして父になる』も元々の子供を取り戻すのだけれども、今まで縁があって一緒に暮らしてきた子供のことを忘れられない、というところに通じるものがあると思いますね。そういう広い意味で言えば、私たちは皆が家族なんですよ。
――キム・ギドクさんはカンヌやヴェネチアなどの映画祭で高く評価されていますが、イ・ジュヒョン監督にとって今回の東京国際映画祭への参加はどんな意義がありますか?
イ・ジュヒョン監督:キム・ギドク監督に映画を学べるということだけでも、本当に光栄で夢のようなことです。だからこそ自分なりに一所懸命臨みました。キム・ギドク監督から演出の仕方を学ぶ機会をこの映画が与えてくれ、またそれを通じて自分が成長できたことをとても嬉しく思っています。ひいてはこれから先、自分が映画人としてどのように進んでいくべきかということも学べたのではないかと思います。もちろん、韓国内で最初に公開するのもいいことだとは思いますが、アジアで同じような痛みを共有してもらうという意味では、国内で上映されるのとは違った意味が生まれるのではと考えていますので、ありがたいことですね。
――本作は韓国と北朝鮮の両国が抱える問題を扱い、残酷な描写もある。その一方で北朝鮮スパイの偽装家族が軍服を着て勲章をもらっているシーンなど、シリアスであればあるほど滑稽だったり。その辺りのさじ加減はどんな具合に?
キム・ギドク:映画にはドキュメンタリーとドラマがあり、本作はドラマなのである意味、意図的にナンセンスにするフィクションの部分が必要だと思います。例に挙げてもらったシーンのように、実際にはありえない場面もそれによって北朝鮮の体制が端的に表現できますし。そうやって観客の方々の理解の助けになるのであれば、ナンセンスなシーンも必要かと。本作のような偽装家族が実際にいるかどうかはわかりませんよ。ただ、映画の中ではメッセージを伝えやすくするために、ああいう家族を作る必要がありました。あのフィクションが“魅力”であり、“手段”だと思うのです。

イ・ジュヒョン監督:悲しみを表現する時に悲しさだけを伝えようとすると、逆に伝わりきらないということが生じます。ちょっとした笑いと悲しみを衝突させることによってそのシーンがおかしくもなり悲しくもなる。あの軍服のシーンも、みんな神妙な顔をしているのが妙におかしかったり(笑)。人間の性のようなものも際立ちますからね。
取材/構成:佐藤友紀(日本映画ペンクラブ)
※『レッド・ファミリー』は、第26回TIFF コンペティション部門観客賞を受賞しました!
受賞結果一覧
コンペティション
『レッド・ファミリー』
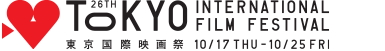







 Check
Check
