10/23(水)ワールド・フォーカス 台湾電影ルネッサンス2013『失魂』上映後、チョン・モンホン監督をお迎えしてQ&Aを行いました。

Q: ジミー・ウォングさんをどのような理由で起用されたかをお聞きしたいと思います。
チョン・モンホン監督(以下、監督):ジミー・ウォングさんは私たちの子どもの頃のアイドル的な大スターでした。脚本を書いているときに、これをジミー・ウォングさんが演じてくれたら、とてもクールじゃないかと思いました。
それから彼に連絡をしてみたのですが、すぐに返事がきませんでした。彼はスターですから、それは当たり前だと思います。後で知ったのですが、その時彼はご病気だったそうです。
お返事いただいてからは、これは絶対彼に演じてもらいたいと思うようになりました。彼としても、出演していただけるということだったのですが、身体の方がどうなのかということが心配でした。結局クランクインの2週間前に決心していただいたのです。ジミーさんがオッケーをくださらなければ、この映画は撮らなかったかもしれません。
Q:日本でも、ジミーさんは70年代の映画に接するきっかけになった方です。
映画の舞台についてですが、非常に印象的な山の斜面をモノレールが走っていましたが、あの場所はどこですか?
監督:台湾の中部の山奥なのですが、ずっと霧が出ている場所がほしいということでプロデューサーか製作が探してきてくれたのです。本当に1年中霧がかかっている場所です。元々、モノレールのようなものはなかったんです。実はモノレールは日本が作ったもので、それを使いました。
Q:最初に出てくる日本料理屋は台北ですか?
監督:はい、台北の高級ホテルにある日本料理のレストランです。
Q:とても色彩が綺麗だったのですが、撮影しながら色彩をあえて置いてみたとか、またはあえてそういった色彩を狙って撮ったということはありますか?
監督:これは実際の風景と同じで、美しいところなのです。美しいというのは人生もそうなのですね。人生が平凡であろうと、平凡でなかろうと美しい部分がある。ただその美しさの中にきっと暗い部分もある。大抵は美しいものというと、人を励ますことや愛情を賛美するようなストーリーになるわけですが、僕にとってはそれとは違った、暗い人生を描きたかった。ただ、どんなに暗い話であっても美しい絵で撮りたいと思いました。その美しさと暗さのちょうど対比でしょうか。
Q:最後のクレジットで、殺人事件のような名前が出ていたような気がするのですが、勉強不足で申し訳ないのですが、このストーリーが本当にあった事件を脚色したのか、または小説を題材にしたものなのか、教えていただけますでしょうか?
監督:これは、原作はありません。ただ、友人の「3人の猟銃を持った人」という話を元にしています。それは最後に息子がお父さんに語った不思議な話です。それは実際に私の友人が中国のシルクロードで体験した話なので、それを映画のエンディングに使わせてもらいました。その3人の猟銃を持った男と、姉さんなど3人殺されますが、その3人との関連ということで、人間の因縁といったものを描きたかったのです。
Q:夜中に息子が山の中で出会う、枝を拾っている人がいました。伝言人と書いてありましたが、あの人はどういう存在の人なのでしょうか?
監督:三池崇史さんの作品に比べたら全然怖くないと思います。(笑)メッセンジャーはチュアンの心の善の部分を表すものです。どんなに悪い人間にも心のどこかに善の部分があって、それが悪い道へ進むのを止めるのです。そういうものを普通は見ることも聞くこともできませんが、彼は精神が崩壊するのを防ごうとする人です。

Q:とても暗い映画ではありますが、希望がみられます。監督もそういうものを意図して作られたのでしょうか?
監督:人生はどんなに暗くても最後には希望、明るいものがあるものだと思っています。だから暗いばかりでない、そういう人生を送ってほしいというのが私の願いです。
Q:スタッフの中に「中島長雄」という撮影監督の名前がありますが、彼は?
監督:あれは実は私自身なのです。私はカメラマン出身でして、自分につけた「中島長雄」という名前です。大島渚さんを連想して「中島」とつけ、「長雄」というのは野菜売り場にいそうな、いかにもダサい名前ということでつけてみました。
Q:演出しながらカメラも覗くというやり方だったのですか?
監督:実際にはカメラを覗かず、モニターを見ていました。最初はカメラマンで、次に監督をするようになって、誰も私のカメラマンをやってくれないので自分でやるようになりました。カメラマンだけでなくて、監督をやってカメラマンもやるほうが非常に早い上に非常に自在であるということを発見しました。
Q:音楽がヒッチコックを思わせるものでしたね。
最後にチュアンの父が入った養老院で、台湾では有名な流行歌の歌手さんが出てきて、エンディングでは歌を聞かせてくれるわけですが、彼は実際に現在もそういった慰問活動をされているのでしょうか、そして彼をどういう目的で使われたのでしょうか?
監督:ヒッチコックを意識してはいませんでした。最後に歌を歌っているのは確かに、50~60年代に有名な歌手だった方です。当時は台湾語の歌が禁止されていました。今、彼は80代だと思います。実際にお仕事はされていないようですが最後に歌って頂きました。
かつて有名だったひとが養老院で歌っているという場面を撮りたかったのです。
Q:チョモン監督はアメリカで勉強なさったのでアメリカ映画も詳しいのですが、シカゴの美術館の付属大学ですよね?アピチャッポン監督も同じ学校ですね。
監督:そうですね、わたしより3,4年後だと思いますが。大学というのは非常に面白いところで、普通にフィルムの勉強をするところではないのです。ですからあの大学はニューヨーク大学やカリフォルニア大学とはちょっと違うのです。私たちはそこで実験的な映画を勉強しました。
Q:作品中の自然や動植物についてお聞きしたいのですが、個人的にはアメリカのテレンス・マリックを思わせる描写だなと思いました。あの自然描写を作品中にちりばめることでどういう効果を狙ったのかということと、日本料理屋での魚の描写やシリアスなシーンでムカデが胸元を這っていたり、土のうえに気持ち悪いミミズのような生き物が映し出されたりしていましたが、そういった動植物はどういった観点で選ばれたのでしょうか?
監督:私は人間も自然の一部だと思っていて、昆虫も同じだと思っています。人の死というのもこの昆虫の死と同じくらいに脆い物です。だから土のなかのミミズのように、人間は非常に曖昧で恐ろしいものでもあるという。特に何かを強調したいと思って撮ったわけではないのです。例えば日本料理のシーンでも、描きたかったのは魚の頭と骨の区分なのです。実際に生命とは弱いもので、肉がなくなっても実はまだその瞬間に在る、存在しているというものではないかと。私にとって肉体とは家で、誰がそこに住んでいるのか、そこに住んでいる人間は住む前は何だったのか、住む前と同じ人物だったのか、そしてその人物は「彼自身」を変えるのではないか。自分が住んでいた家に帰ってきて、そこに誰も住んでいないのをみつけたような、誰かが住んでいて「ここは俺の家だ」と言われたらあなたはどうするか。それがこの映画でおおよそ私が言いたかったことなのです。

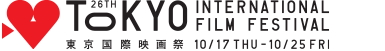







 Check
Check
