トークセッション“メジャーってなに? インディペンデント出身監督の目標設定とは?” (前編)
奥原浩志監督×松江哲明監督
司会:矢田部吉彦(TIFFプログラミング・ディレクター)

2012年10/24(水)、PFFグランプリ受賞作品『くじらのまち』上映後、昨年の『歓待』シンポジウムと同様に、第25回TIFFコンペティション部門に『黒い四角』を出品の奥原浩志監督と同部門に『フラッシュバックメモリーズ 3D』を出品した松江哲明監督によるトークセッションが行われました。この対談は3回に分けての掲載です。
映画祭開催前に行われた“スペシャル企画~東京国際映画祭「日本映画・ある視点」部門 座談会 前編・中編・後編”とあわせてお読みください!
矢田部:トークショーの趣旨を簡単に話したいと思います。まず、松江監督と奥原監督がコンペティション部門に出品しているので、何かできたらいいと思いました。それから、「日本映画・ある視点」の座談会を劇場の方々を集めてやったのですが、その中である劇場の支配人が、「監督の1作目を劇場にかけることはあるが、公開してその後、監督がどうしたいのかわからないケースが多い」と言っていました。そこで、たくさんの若い人々が映画監督になりたいと思いPFFに出品し、でもその後、どういうキャリアの可能性があるのかというこの問題は、いつ考えても必要なことなのではないかと思いました。
10年以上のキャリアを持つ奥原監督と松江監督が、いかにして現在のポジションにたどり着いたのか、今の若い監督・クリエーターたちに、何かしらの刺激を与えることができたらと考えました。さらに「日本映画・ある視点」という部門についても我々は試行錯誤していまして、インディペンデント映画を応援するということを標榜していますが、その応援する人たちに、その後、商業映画を撮れるような人になってもらいたいのか、表現者として、芸術家として大成してもらいたいのか、方向性としても色々なことが考えられるわけです。今の若い日本の監督をどういう風に応援したらいいのだろうかというところも、お二人に伺っていけたらと思います。
それでは、奥原監督からよろしくお願いします。
奥原監督は1968年生まれで、現在43歳でいらっしゃいます。93年に、当時24歳で『ピクニック』という作品で “PFFアワード”に入選されました。この『ピクニック』を撮られたときの立場を教えていただけますか?
奥原浩志監督(以下:奥原監督):フリーターでした。
大学を卒業した後に1年くらい映画館で働きました。それまでは、自分で作ろうという気はまるで無かったのです。本当に考えたことすら無くて。でも、その映画館で働いている時に撮りたくなったのです。

矢田部:その作品がPFFに入選(『ピクニック』はPFFアワード1993で日本船舶振興会賞(キャスティング賞)、シャンテ賞(観客賞)を受賞)するわけですね。それはどういう影響を奥原さんに与えましたか?
奥原監督:それまで映画を見るのが大好きだと言っても、日本映画、自主映画のことは全く知らなかったし、PFFのことも実は知らなかったのです。8ミリでしたが、僕が監督をやって、もうひとりキャメラがいて。そのキャメラをやっている人間がPFFに出そうと言って応募しました。それまでの人生で自分が作ったものが人に評価されてるということがなかったものですから、その気になっちゃったんですね(笑)。
矢田部:翌年に間髪おかずに『砂漠の民カザック』を撮られました。
奥原監督:ほかにすることもないので、すぐやりました。
矢田部:そしてPFFに2年連続で入賞(『砂漠の民カザック』はPFFアワード1994で佐藤工業賞(録音賞)を受賞)、それから『タイムレスメロディ』(99)という作品で、一気に世の中に出てこられるわけです。私も奥原さんの名前を『タイムレスメロディ』という作品で初めて知った記憶があります。PFFアワードの94年と『タイムレスメロディ』の99年の間は、どういう形で過ごされていたのでしょう。
奥原監督:ずっとアルバイトしていましたが、その時期はちょっとつらかったですね。短編は作っていたのですが一番つらかったのは、『タイムレスメロディ』を撮ることが決まってから、いつ撮れるようになるか教えてもらえなかった、撮り始めるまでの2年か3年の期間でした。2年後を目途でと言われれば、それなりの準備も出来ますが、連絡も来なくなったりして。
まあ、お金が集まってこなかったことが理由なのですが。その辺の待っている時間がものすごいストレスで、実際、『タイムレスメロディ』を撮った時もストレスが結構ありましたね。
矢田部:映画監督になろうと思っていなかったと最初に言いましたが、映画を作ろうという思いはずっとあったということですか?
奥原監督:映画監督というポジションに就くということであれば、もっと別のやり方がいいと思うのです。まず、助監督をやるとか。その方法だと、自分で映画を作りたいということにはならなかったでしょう。
矢田部:2年前、松江さんに今後の夢や目標はなんですかと聞いたところ、「映画を作り続けることです」と言ったことがこのトークショーを行うきっかけにもなっているのですが、とにかく奥原さんも「作り続けていたい」と思われた。青臭い質問ですが、それは「情熱」だったのですか? それとも「仕事」にしたいと?
奥原監督:「情熱」です!(笑)
矢田部:『タイムレスメロディ』が第9回PFFスカラシップ作品として製作され、海外の映画祭でも評価されました。その時の感触をいま振り返ると?
奥原監督:作品に全く満足できなくてつらかったですね。作り方も自主でやっている頃と全然違うわけです。それに自分一人が未熟で、すごく違和感がありました。あれだけの規模の映画は、自分の力だけではできないし、あの頃は周りの人に対しても結構無礼なことを言ったりふるまったりしたはずです。反省もしているのですが、でも違和感があって。映画を作るって、もっと簡単なはずなんじゃないかという思いがかなり強くありました。それで、一回それをやろうって思い、また翌年すぐに作ったのです。
矢田部:それが『波』という作品になるわけですね。2001年で、監督は33歳ということです。『波』は手応えはありました?
奥原監督:また新しい体験でした。このときは大森立嗣(『タイムレスメロディ』助監督、『波』プロデューサー・出演)と、もうひとり、その前にデビューしていた渡辺謙作(『波』プロデューサー・主演(乾 朔太郎名義))と、毎日のように友達が集まりました。他にも映画関係で、撮影助手や美術助手をやっていた人間が集まりましたが、この時は逆に監督する責任を初めて体験しました。
矢田部:監督としての自覚が強まったような感じですか?
奥原監督:みんなが集まって助けてもらった映画で、映画の撮影が終わりになっていくほど、ここまでみんな一所懸命やってくれて、これでもし作品がダメだったらどうすればいいんだろう、結果が出なかったらどうしたらいいんだろうと。そのプレッシャーがすごかったです。だから撮影が終わっても暗い気持ちでしたし、編集しているときもつらかったですね。
矢田部:そして、2004年に宮崎あおいさんを主演に迎えて『青い車』という作品です。これは『タイムレスメロディ』から『波』に至る動きがあって、『波』から『青い車』はどのような展開でしたか?
奥原監督:お話しをもらって撮ったのですが、キャストが豪華な割にはかなり低予算で、プロダクションが製作プロとして入りましたが、この時もつらかった。
僕は助監督経験があるわけでもないし、映画製作に関してプロとしてやっていくには、 “うぶ”だったということを学ばされた作品です。本当に自分で作りたいものを作るためには、自分がやりやすいように撮れる環境を作る。環境を整えることをやらなければいけないことが、実はすごく大事なことだと学んだ現場でした。
矢田部: 93年で『ピクニック』、2004年で『青い車』。映像を作り続けることで、ある程度「食べていけるかも」と思われたのはどの時点ですか?
奥原監督:今まで一回も食っていけたことがないのですけれど(苦笑)。
矢田部:そこは今の若い人にも参考になりますね。『青い車』を撮り終わって、このままこういったクラスで行けるという感じはありましたか?
奥原監督:それは、僕がどうというより周りの判断だと思います。作品を見て、「この監督とやりたい」という要望があればそのままいくのでしょうが、これまでは残念なことにそういうことはなかったです。
矢田部: 2007年、『16 [jyu-roku]』という作品になるわけですね。『青い車』から『16 [jyu-roku]』の展開は?
奥原監督:つねに企画はあって完成した脚本もたくさんあるわけですが、どの企画も進まなかったですね。『16 [jyu-roku]』は、『赤い文化住宅の初子』(07)のDVDの特典映像用に頼まれたものです。クランクインの一週間前に、それまでは50分くらいでと依頼されていたものを後から長編となりました。小さな作品だったのですが終わった時にそれまでの経験、その上、ものすごい低予算ですが、映画監督として自分がこの先やっていく準備が整ったのかなという感触があったのです。その感触は自分にしかわからないのですけれど。
矢田部:そこの時点だったのですね。またあとで戻ってお聞きします。ここで松江さんにお話を聞いていきたいと思います。松江さんは日本映画学校に入られたわけでそもそも映画監督志望だったのですか?
松江哲明監督(以下:松江監督):はい、劇映画監督志望でした。

矢田部:いつごろから劇映画監督になりたいと?
松江監督:それはもう小学校の頃とか幼い頃から映画が好きでしたし、ジャッキー・チェンのファンでジャッキー・チェンになりたいと(笑)。本当にそういうレベルですね。
矢田部:ジャッキー・チェンになりたいと思った人間の中で、映画監督になれる人は多分、一万人に一人なわけです(笑)。
松江さんは77年生まれで現在35歳。日本映画学校の卒業制作として『あんにょんキムチ』(99)を作られました。『あんにょんキムチ』(99)を撮られたのは23歳ですか。
松江監督:卒業制作なので、製作自体は20歳から21歳にかけてです。1年間かけて作りました。公開されたのが23歳のときです。
矢田部:この作品はPFFには出品しましたか?
松江監督:ぴあには高校生の時に出しました。落選しましたけれど。
矢田部:どういう作品だったのですか?
松江監督:上映しないので言いますが、当時好きだった北野武さんの真似事というか、おもちゃの鉄砲でバンバン撃っているようなやつでした。Hi8 (ハイエイト)で撮っても高校生がスーツ着ておもちゃの鉄砲を撃っていたのではギャグにしかならないんです。それでまあ、挫折ですね。だから『あんにょんキムチ』を撮るまでに映画学校で企画を出したり、劇映画をやることに挫折しています。
自分にはもう劇を作る才能がないと感じて、それで唯一できるというか、興味があって作れると思ったのがドキュメンタリーでした。その当時デジタルビデオがちょうど出てきた頃で、映画学校の先生をしていた安岡さん(安岡卓治)が、森さん(森達也監督)と一緒に『A』(98)を作ったり、アダルトビデオでは平野勝之さんの『由美香』が劇場公開されていて、こういうドキュメンタリーなら僕でもできるかなと。『あんにょんキムチ』を作って、この作品が劇場公開されなかったら映画は辞めようと思っていました。
矢田部:21歳のときにもう勝負をかけたわけですね。
松江監督:劇場公開するという目標を持って作った映画でした。
矢田部:ドキュメンタリー監督だと「食える」のかなとか、学生時代の考え方はどんなでしたか。
松江監督:「食える食えない」はあまり考えていなかったですね。今でもあまり考えていないところがあるんですけど。ただひとつ思ったのは、映画学校の先輩たちがドキュメンタリーでデビューする人が多かったですね。
セルフドキュメンタリーが多かったのです。ちょうど、『妻はフィリピーナ』(寺田靖範監督、94)、『ファザーレス 父なき時代』(茂野良弥監督、99)、後輩ですと『home』(小林貴裕監督、01)。ただ、その人たちは2本目を撮っていないんですね。ですからセルフドキュメンタリーで自分自身のことを描くとデビューはできるけど、2本目を撮れないということがわかっていたんです。けれど、とにかくデビューするということが目標で、「食える食えない」より言葉は悪いかもしれないけれど、(彼らを)反面教師にしていた部分はあります。セルフドキュメンタリーでデビューすると次が撮れないなら自分は違うことをしなくてはという意識はありました。
矢田部:セルフドキュメンタリーでデビューして、松江さんのようなキャリアを築いている人はおそらくひとりもいないでしょうね。それだけ松江さんは画期的な道を歩んでいると思います。
松江監督:でも、その時言われた「次どうするの」という言葉だったり、佐藤真さん(ドキュメンタリー映画監督)に言われたことだったりが、逆説的にすごく力になりました。何でもやろうという気持ちがあったので、そのあとVシネマで流行っていた『呪いのビデオ』(『ほんとにあった!呪いのビデオ』99~、8・9・10・special2・を松江監督が構成・演出)シリーズをやったり、アダルトビデオもやったりとか、とにかく何でもやりましたね。面白いものさえ作ればどうにかなるという気持ちはありました。
→中編につづく:次回では、松江監督より『あんにょんキムチ』で目標を達成してからその後、奥原監督から『黒い四角』を撮影するまでのお話しを伺います。お楽しみに!

●邦画ファン、映画製作関係者必見!!スペシャル企画~東京国際映画祭「日本映画・ある視点」部門 座談会
→前編 →中編 →後編
●こちらも必読!第24回(2011年)TIFFにて行われた、第23回「日本映画・ある視点」作品賞受賞作品『歓待』のシンポジウムの模様
→TIFFから世界を旅した作品『歓待』の1年の軌跡を辿るシンポジウム!
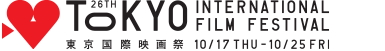







 Check
Check
