海外公演のチャンスをつかんで大喜びのアマチュア劇団員たち。が、主人公を演じる若い女優の父親が、海外に行く事に猛反対。パスポートを隠して、実力行使に出るが…。イランの現代若者事情をリアルに映し出す『ルールを曲げろ』のベーナム・ベーザディ監督と、ヒロインを演じたネダ・ジェブライーリさんにお話を聞きました。

――演劇に夢中になる娘を理解できず、厳しく反対する父親。こういう親子の感覚のズレなど、日本の文化に似ていると思いました。
ベーナム・ベーザディ監督(以下、ベーザディ監督):イランや日本に限らず、すべての文化にこのようなものがあると思います。時代が変わったので少し形は違いますが、誰しもが経験した事のある問題でしょう。
――この物語を作るきっかけは?
ベーザディ監督:イランは、人口の75%が35歳以下の若者なのです。ですから、どこに行っても若者が目に入る。特にイランの若者は、社会的にも政治的にも、文化やスポーツにおいても様々な活躍に参加しています。つまり、つねに若者が目立っている社会で生きていますので、当然、彼らに目がいってしまうのです。
――TIFFの公式プログラムには、親子、家族の闘いが、自由を勝ちとる闘いのメタファーでもあると書かれていますが?
ベーザディ監督:それは否定しません。でも、それは書いた方のひとつの意見だと思っています。私は映画を作る時に、観客にいろいろなシチュエーションやいろいろな人間関係を見せて、それぞれが自分なりに感じるように作っています。
――親子に限らず、年配者と若者の摩擦はどこの社会にもあるもので、とても普遍的なテーマだと思います。さらに観客の年齢や立場によって、感情移入する人物も違ってくるようです。
ベーザディ監督:映画の語り口にもよりますが、強いメッセージ性があると見る側は最初から好きか嫌いか、受け入れるか受け入れないかをはっきりと決めてしまうものです。私自身はそういう映画はあまり好きではありません。私が好んで見る映画は自分も参加できるような映画なので、自ら作る作品も作家性を重視しながらも、カメラの存在を消して物語を綴っていければいいなと思います。
――本作も、その手法ですか?
ベーザディ監督:はい。自分の色を濃くせずに、監督は存在を消した方が、観客が参加していろいろな事を考えやすいのではないかと思いました。

――ネダ・ジェブライーリさんは、厳格な父親に海外公演に行くことを反対される新人女優シャフルザードを演じましたが。
ネダ・ジェブライーリ(以下、ネダ):初めてこの脚本を読んだ時、この映画は私が主役ではなくアマチュア劇団の団員みんなが主役だと思いました。ということは、自分は目立とうとせずに、ひとりの女性をものすごくリアルに演じていけばいい。そうすれば、物語の半ばで姿を消しても存在感は残ると思いました。役者はどうしても目立ちたがりなのですが、今回、それは抑えようと思ったのです。その成果が画面に出ていたらすごく嬉しいなと思います。
――稽古場にしている家の中を撮った長回しのカットが圧巻でしたが、演じるのは難しかったでしょうか?
ネダ:私はこの作品がデビュー作で、女優としての経験も浅いのでとても難しかったです。もちろん何回も何回もリハーサルは重ねていましたが…。いざ本番で自分のセリフを言いながら演じるとともに、カメラの位置を確認していく。カメラが後ろにある時など位置を確認しようもないのですが、それでも1ミリか2ミリでも位置が外れれば撮り直し。ほかの役者さんにももう一度やり直してもらわなければいけないので、辛かったです。リハーサルを何回もしたのに普通に歩いていたら、監督から「ゾウみたいに歩くのはダメだ」とか、「走っているみたいだ」と言われて…。歩くスピードもコントロールしつつ、相手役との位置も体と顔の角度にも気をつかい、セリフを言いながら演じるというのは最初は本当に難しいんです(笑)。
ベーザディ監督:映画が完成した今だから言えるのですが、出演者のほとんどがこれがデビュー作だったり、小さい役を数回演じただけの人だったりしました。ですから、役者たちは長回しにチャレンジしたいという気持ちと同時に不安もあったと思います。そして、もちろん私も不安でした。彼らがどれくらいできるのか、カメラの動きやポジションをきちんと意識できるのか、自然にリアルに演じられるのか、と。

――画面には、劇団員たちの情熱や充満する熱気、そしてそれぞれの悩みや戸惑いが映し出されていたと思います。ちょっとドキュメンタリーの味わいも感じました。
ベーザディ監督:嬉しいです。でも、そうするには私自身、大変でした(笑)。いろいろなことを考えてすべてをデザインしましたから。まず、デザインをしたのはコンポジションです。状況をどう作るのか、カメラの位置はどうするのか、みんなが動く中でカメラに誰が映って誰が映らないのか。セリフを言っている役者の表情はどうするのか…。リハーサルをしている時から、どこから初めてどこで終わるべきか決めていました。でもその一方で、役者たちに隠しておく事も必要だと思いました。リハーサルに慣れてしまうといざ本番という時に、新鮮味を失ってしまう。そうなると逆に不自然に見える事もありますから。とにかくこれまでの作品とは違い、より多くの事をいっぺんに考えなければなりませんでした。
――緻密な計算をしつつも画面では自然に見える、ということですね?
ベーザディ監督:そうです。見る側にはこの人たちはそこに住んでいる、生きているということを感じさせるように。要するにカメラは存在しない、監督はいないという撮り方でした。
――コンペティション部門に参加していただいた感想は?
ベーザディ監督:呼んでいただいてとても嬉しいです。賞はいただけるものならば、ぜひに!(笑)
取材/構成:金子裕子(日本映画ペンクラブ)
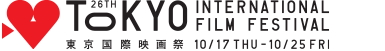







 Check
Check
