
10/18(金)『ある理髪師の物語』の上映後、ジュン・ロブレス・レナ監督、ペルシ・インタランさん(プロデューサー)、ユージン・ドミンゴさん(女優)が登壇し、Q&Aが行われました。
1970年代、マルコス政権下のフィリピンの片田舎。代々営んできた夫の床屋を継いだ未亡人のマリルー。彼女は周囲の偏見と闘いながら店を繁盛させるうち、独裁政権下の腐敗を目の当たりにし、反政府運動に加担していく。
昨年、『ブワカウ』で第25回TIFF〈アジアの風〉スペシャル・メンションを受賞した若き俊才、ジュン・ロブレス・レナ監督の最新作で、主演は『浄化槽の貴婦人』『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ』でお馴染みのユージン・ドミンゴ。Q&Aではドミンゴさんが撮影に参加するまでの秘話が語られ、チャーミングな語りに場内は魅了された。
ジュン・ロブレス・レナ監督(以下、監督):皆さん、こんばんは。作品を観に来て下さり、ありがとうございます。昨年も『ブワカウ』(第25回東京国際映画祭〈アジアの風〉スペシャル・メンション受賞)で、映画祭に参加させていただきました。新作を持って戻ってくることができて、信じられない思いです。しかも今回は、コンペティションで上映できて大変光栄です。
ユージン・ドミンゴさん(以下、ドミンゴさん):本当にお越し下さりありがとうございます。会場にいらっしゃるフィリピンの皆様にも感謝します。これは皆様のために作った映画です。いま初めて作品を観て胸がいっぱいです。トーキョーは天気も穏やかで大好きな街なんです。
ペルシ・インタランさん(以下、インタランさん):ワールド・プレミア上映にお越し下さり、ありがとうございます。会場で一緒に観ていて、皆さんのリアクションにワクワクしました。
矢田部PD:まず、なぜこの時代の物語を撮ろうと思ったのでしょう?
監督:この作品はトリロジー(3部作)のうちの1つで、『ブワカウ』に連なる2番目の作品です。3部作のテーマは孤立で、死ばかり考えている人物を主人公にしたものです。今作では1970年代、マルコス政権下のフィリピンで、周囲の期待を集める女性を描いています。
いま製作中の作品は14歳の孤児を主人公にしたもので、実は父親は存命する神父であり、唯一残された肉親と過ごすために信仰の道に入るという物語です。各作品はアイデンティティ、自由、セクシュアリティを扱っています。1970年代のフィリピンは激動期でしたが、あれから40年経ったいまでも、実は同じ問題を抱えているのだと感じています。

矢田部PD:ドミンゴさんは脚本を読んで如何でしたか?
ドミンゴさん:少し長くなりますが、私がキャストに選ばれた裏ばなしをお話しましょう。監督とは長い付き合いですが、映画に出演するのにも長い経緯がありました。
インターネットで検索すればわかると思いますが、私はフィリピンでは主にコメディ映画に出演しています。もう何年もずっとコメディエンヌとして活動しているのですが、ある日のこと、プロデューサーからフェイスブックにメッセージがありました。自分がプロデュースするシリアスな内容の脚本があるけど、読んでくれないかというものでした。その時にレナ監督の作品であることも告げられました。
当時はメジャー・スタジオの作品を5本も抱えていたので、彼の作品に出る余裕はなく、脚本を読むゆとりすらありませんでした。そこで断ったのですが、1〜2年が過ぎた頃、主役のオーディションを開催していると耳にしたのです。相変わらず忙しかったのですが、「主演は決まったの?」と連絡すると「まだ」という返事で、「ぜひ脚本を読んでみないか」と改めて言われました。
そこでEメールで脚本を送ってもらいましたが、なぜか分からないけどデータが開けない。もう一度送ってもらい、やっと開いて読み始めたら、すっかり虜になってしまいました。
皆さん、マリルーが市長を刺す場面で驚きの声を挙げましたが、私も皆さんと同じ反応をしたんですよ(笑)。市長の奥さんが飛び降りる場面でまた「キャー」と叫んで、読み終わった時には思わず拍手喝采していました。
そこで監督に直接電話をかけたのです。「大変いい脚本だわ。フィリピンという国、そこで生きる女性にとって、普遍的なメッセージを込めたすばらしい物語ね」と称賛を伝えたのです。そしてもう一度、「女優は決まった?」と聞くと、「まだなんだ」という返事でした。実は、私が引き受けるのを監督は待ち続けてるんじゃないかと思いましたが、うまくコミュニケートできないまま会話は終わってしまいました。
もうこうなったら仕方ありませんよね。「私を採用しないの?」と矢継ぎ早にメールすると、「引き受けてくれるの?」と返事があって、ようやく役に決まったのです。
(場内拍手)
ドミンゴさん:長編ドラマに出るという長年の夢がこうして実現できたのです(笑)。ほんとに演じていて楽しかったです。

Q:いまから40年ほど前の物語ですが、どんな資料を用いて脚本を書いたのですか?
監督:1970年代、独裁政権下のフィリピンは、個人的にも興味深いものがあります。そこには家族の問題がありました。私の場合、母方の親族に解放軍に関与していた者がおり、報道で知ることではなく、家族が実際に体験したできごとでもあったのです。戒厳令の状況下は人ごとではなく、家族が実際に体験し、感じていたことです。政変の結果、何がどう変化したのかを伝えることが重要でした。
1970年代を生きる女性がある期待値を背負ってしまい、苦しみながらも、自分の意見が言えるようになる。そうした姿を通じて、女性が社会の中で自分の場所を如何に見いだしていくのか、また家族の問題や反乱軍といった諸問題は当時だけではなく、いまに連なる問題でもあるのだと訴えたかったのです。
Q:ドミンゴさんは脚本以外にも惹かれた部分はありますか?
ドミンゴさん:まず女優として脚本と恋に落ちました。そして監督を信頼し、そのヴィジョンを理解しました。フィリピン人を描くという目標も明確であり、映画出演に必要なすべての要素が揃っていました。女優であること以前に女性であり、すべての女性は愛され、尊敬されるべきだというメッセージに心から共感したのです。

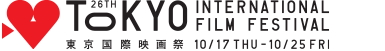







 Check
Check
